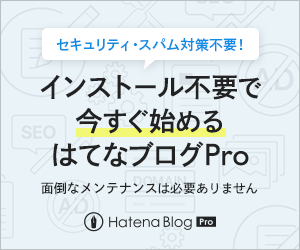こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
館山市の祭礼といえば、千葉県無形文化財の「やわたんまち」が有名。
でも、安房神社のお祭りは1300年の歴史をもつ南房総1の古さを誇ります。
今回は安房の一の宮である「安房神社」の例大祭をピックアップ。
ではでは早速!
安房神社例大祭について

安房神社境内様子
安房神社は、館山市の神戸(かんべ)地区にあたり、市の南に位置します。
南房総国定公園を有し「野鳥の森」などがあり自然豊かな地域。
安房神社は、今でもこうした自然豊かな森に囲まれ、安房の一の宮としての威厳を誇っています。
館山市・南房総市が「安房国(あわのくに)」であったころからの「一の宮」です。
「一の宮」とは、この一帯の神社の中で最も社格が高い神社のことで、一国に一社しか存在しません。
安房神社例大祭は、この安房神社とその周辺の地域で開催されるお祭りです。
大変長い歴史があり、お祭りは1300年以上とされます。
祭礼日
毎年8月10日が祭礼日で、前日の9日は子供神輿が出祭、10日は安房神社の神輿が出御。
周辺地区の神輿6基や屋台2台も繰り出し神戸祭礼とも言われます。
祭礼内容
本来ならこれに併せて、周辺神社から神輿が境内まで来ていましたが、担ぎ手の不足から現在は行われていません。
残念な事に各神社それぞれで例祭を行っています。
管理人の中では「レッドリスト祭礼」です。
大変由緒ある祭礼なのですが、この辺の過疎化はとっても深刻。
今も定期的に各地区が参加するなどして、お祭りを盛り上げています。
参加地区
かつての地区も含め大神宮、犬石、佐野、洲宮、中里、滝口、布良、神余、相浜、白浜、松岡、竜岡、布沼、藤原といわれています。
3年に一度各地区が安房神社に出祭。
山車・神輿等をご紹介
大神宮(安房神社)

安房神社の神輿
例大祭の中心である安房神社の御膝元です。
菊の御紋を掲げる神輿があります。
普通はモミ・サシをメインとする神輿がほとんどなのですが、安房神社の神輿は兎角走ることをメインに考えられているため、重量が軽いのが特徴です。
現在のものは明治時代に地元の大工作。
神輿の様式的には室町時代から江戸時代初期にかけてのものを受け継いだ形となっています。
神輿の歴史については、「安房神社の神輿から神輿の歴史」へどうぞ!
安房神社例大祭の他に、安房国司祭(やわたんまち)にも鶴ヶ谷八幡宮に奥さんの神様である洲宮神社、下立松原神社が「南三社」としてともに出御します。
 大神宮が出祭する祭礼
大神宮が出祭する祭礼
犬石(犬石神社)

仮屋奉安の犬石の神輿
安房神社の北側の広い範囲にある地区。
犬石神社を祀り、神輿を有します。
御祭神は月読命(つくよみのみこと)。
安房神社、下立松原神社に次いで3番目の大きさの神輿。
渡御の際には瓔珞(ようらく)や葺き替えしなども取り外してすっきりとした姿となりますが、室町時代の様式を残しています。
作製された時期は江戸中期ごろともいわれています。
かつては安房神社例大祭に参加していましたが、現在は出祭はしていません。
佐野(熊野神社)

仮屋奉安の佐野の神輿
佐野地区は安房神社の北方で山間にあり、そのほぼ中心にに熊野神社があります。
明治26年に作られた神輿は、朱と黒の漆で見事に塗られています。
後藤利兵衛橘義光によって彫られた彫刻は、細部にまで渡り作られ神輿を飾っています。
彫刻内容は「神武東征・天岩戸開き」が題材。
昭和三十年代中頃以前は、10月9日に熊野神社例祭が行われていましたが、その後8月10日の安房神社例大祭に参加するようになりました。
しかし、担ぎ手不足等で現在は佐野地区単独でのみ例祭を行っています。
洲宮(洲宮神社)

洲宮神社境内様子
安房神社よりも少し内陸に入った辺りで、洲宮神社周辺地域を指します。
洲宮神社は安房神社の后神である「天比理乃咩命(あまのひりのめのみこと)」を祀っています。

仮屋奉安の洲宮の神輿
安房の国二の宮として安房国司祭(やわたんまち)の際には安房神社とともに入祭します。
屋根の勾配がやや深く神輿の様式は江戸風で、平成17年に行徳の浅子神輿店にて大修理されました。
8月10日の安房神社例大祭に参加していましたが、担ぎ手等の不足で8月第一日曜日に単独で洲宮神社祭礼を行っています。
 洲宮神社の論社、洲崎神社について
洲宮神社の論社、洲崎神社について
中里(八坂神社)

仮屋奉安の中里の神輿
安房神社のすぐそば北側にあり、八坂神社を祀ります。
安房神社例大祭に出祭していましたが、現在は参加していません。
神輿があり、後藤義光作の彫刻が彫られています。
江戸時代後期の神輿か?
滝口(下立松原神社)

下立松原神社拝殿正面
館山市を抜け南房総市白浜に入ってすぐの地区で、下立松原神社を祀ります。
主祭神である天日鷲神(あめのひわしのかみ)は、安房神社の天太玉命(あめのふとだまのみこと)の孫と共にその子孫達が安房に渡って来たと言われています。
そのため安房開拓の神として、安房神社・洲宮神社と並んで「南三社」といわれ崇拝されています。

仮屋奉安の滝口の神輿
神輿は後藤喜三郎義信作の彫刻が所狭しと飾られ、重さは米俵8俵分の480kg、担ぎ棒も7メートルを越します。
モミサシが大変豪快で、祭礼の見どころとなっています。
8月10日の安房神社例大祭にも出祭していましたが、現在は8月1日に例祭を行っています。
安房国司祭(やわたんまち)にも参加しています。
この他に、「ミカリ神事」と呼ばれる「房総のミカリ習俗」として県記録選択無形民俗文化財になっている神事があります。
旧暦の11月26日から10日間(大体1月の中旬頃)行われる祭りで、開拓の時代に農作物も荒らす鹿などの退治をしたことがはじまりと言われています。
昼夜を通して様々な神事が行われますが、このような一連の神事が行われるのは千葉県内では下立松原神社だけだそうです。
祭り期間中に焚かれる火にあたると一年間風邪をひかないとも言われ、家内安全五穀豊穣が祈られます。
神事の期間中にも神輿が出祭し、例祭とは違った下立松原神社の神輿姿を見ることが出来ます。
 滝口が出祭する祭礼
滝口が出祭する祭礼
布良(布良崎神社)

仮屋奉安の布良の神輿
安房神社を過ぎ、海を臨む海岸沿いの地区でその高台に布良崎神社を祀ります。
7月20日前後に例祭が行われ、神輿が担がれます。
かつては安房神社例大祭にも出祭していましたが、現在は参加していません。
神輿は「大天皇」と呼ばれる房総一の重量を誇り、時代を遡るほどその重さは大きかったと言われています。
後藤喜三郎橘義信による彫刻が施され、昭和57年、平成21年に修複が行われています。
昭和天皇の即位式に東京を中心とした周辺地域から1000余りの神輿が皇居前広場に集まったことがあるそうですが、この祭典に布良崎神社の神輿も参加したという話が伝わっています。
神余(日吉神社)

仮屋奉安の神余の神輿
安房神社の南側、南房総市と接するところにある地区です。
日枝神社は延歴23年(804)創建とされる古社で、神余・犬石・大神宮・布良の人たちがの農漁豊穣のために創立したといわれます。
安房神社例大祭に出祭していましたが、現在は単独で日吉神社例祭を行っています。
例祭は7月19、20日で、20日に神輿が担がれます。
神輿は戦後に作られたもので、当初は白木造りだったものを平成8年頃の修復で黒塗りにされました。
19日に行われる「カッコ舞」(※カッコとは太鼓のこと)は、平成8年館山市無形民俗文化財指定されました。
およそ250年前より伝わり「風流の獅子」とも言われます。
境内や地区内を腹につけた太鼓をたたきながら踊りを披露して回ります。
相浜(相浜神社)

相浜の波除丸
布良と同様海を臨む海岸沿いにある地区です。
相浜神社を祀ります。
安房神社例大祭に神輿が出祭していましたが、現在は行っていません。
その際には浜降「磯出」神事の先導役を努めていました。
また、神輿の他に御船の「波除丸」がいますが、曳き手がおらず残念ながらこちらも町内の曳き回しがされていません。
波除丸は、他の地区の御船と比べて水押(船の先端のとがっている所)の角度が緩いのが特徴。
朱塗りの雅な姿で、後部は明治34年に後藤喜三郎橘義信によって彫られました。
明治30年頃、昭和33年、昭和54年に改修。
3月の最終土日に例祭が行われ、境内でお囃子や踊りが行われ海上安全と大漁祈願を祈ります。
 波除丸の写真をもっと見たい方はこちらの記事へ
波除丸の写真をもっと見たい方はこちらの記事へ
根本(白浜神社)

根本の山車
白浜神社を祀り、山車があります。
人形は源範頼で、山車は足回りが高くすらっとしているのが特徴です。
安房神社例大祭に出祭していましたが、現在は参加していません。
神輿があるとの情報がありますが、詳細は不明です。
竜岡(熊野神社)
安房神社のすぐ傍に位置する地区です。
竜岡神社(熊野神社)を祀ります。
例大祭の際に屋台を出祭していましたが、現在は参加していません。
松岡(松岡八幡宮)
竜岡と同じ地区で、松岡八幡宮(八幡神社)を祀ります。
屋台を出祭していましたが、安房神社例大祭には出祭していません。
布沼(厳島神社)
布沼は平砂浦に面する海岸から少し内陸に向かって伸びる細長い地区です。
厳島神社を祀り、かつては安房神社例大祭で神輿が渡御していました。
現在は参加していません。
神輿は戦後作られたもので、特徴は担ぎ棒の組み方。
京都風の組み方をちょっと変えた感じのものだそうです。
藤原(藤原神社)
藤原は布沼と隣接し、平砂浦の海岸から内陸あたりまで続くかなり細長い地域です。
藤原神社が鎮座しますが、藤原地区の住人はもともとは洲宮神社の氏子でした。
安房神社例大祭には現在参加しておらず、8月1日に藤原神社例祭を行っています。
例祭で舞われる獅子舞は「藤原神社獅子神楽(ふじわらじんじゃししかぐら)」と言われ館山市の無形民俗文化財に指定されています。
元氏子ということから洲宮神社に奉納していましたが、昭和23年にこの行事はなくなりました。
しかし、奉納のお礼として洲宮神社の神輿が藤原神社にやってくるのは変わらず続けられています。
詳細は藤原神社 | 一般社団法人 館山市観光協会をご覧ください。
 各地区の例祭の詳細はこちら
各地区の例祭の詳細はこちら
その他参加する祭礼
各地区とも安房神社例大祭の他に、南総里見祭り・安房国司祭(やわたんまち)に参加します。
また、各々の地区で祭礼を行う地区もあります。
詳細は「山車・神輿等の詳細」のそれぞれの地区を観て下さい。
南総里見祭りは毎年必ず出なければならないものでないため、参加したりしなかったりします。
詳細については一般社団法人館山市観光協会の案内を参考にしてください。
安房国司祭(やわたんまち)は、安房神社(大神宮)、洲宮神社(洲宮)が毎年参加します。
「やわたんまち」は千葉県指定の無形民俗文化財ですので、館山市の市役所ホームページや千葉県のホームページなどからも確認いただけます。
< 参考文献・サイト >
安房の一の宮たる安房神社の伝統
安房神社の歴史は大変古く神話時代にまでさかのぼるといわれています。
出雲の国、紀伊の国と並び祭祀を行う重要な国として認められ、一の宮、官幣大社とされました。
安房神社境内には人骨や鏡などが出土した洞窟などがあり、実際に古くから人が往来していた痕跡も見受けられ、千葉県指定の遺跡にもなっており大変貴重な土地でもあります。
はじまりは、四国の徳島(旧阿波)からやってきた忌部氏が、この地に「天太玉命(あめのふとだまのみこと)」を祀ったことが始まり。
例祭は1000年以上も続く祭事で、もともとは安房で各地に散った忌部氏が一同に集まり参拝したことが由縁されます。
中世から近代までの間の資料があまりないのですが、古代より現在に至るまで安房の国一の宮であることは変わっていません。
館山市内にある鶴岡八幡宮がよく知られているため、そちらを安房で一番偉い神社と勘違いされていますが、安房神社は現在でも安房の中で一番社格の高い神社。
その証拠に、鶴岡八幡宮の祭礼時(安房国司祭(やわたんまち))には、渡御した安房神社の神輿は専用の「安房神社遙拝所」に安置され主客として扱われます。
安房神社例大祭は、人口の減少、高齢化が進み周辺地域の神輿の担ぎ手も不足し、現在は神輿や屋台が例年出せない事態になっています。
大変ピンチ!
資料等も少ない!
とっても歴史があるがゆえに、とっても残念な事態。
弱小文化財を応援するまちこ的には、どうにかしたいお祭りの一つです。
かといって何かできるのかといったら、こうしてブログで宣伝するくらいしかできません。
どれどれ、そんなに歴史があるなら見に行ってみようじゃないか、と思われた方。
来て下さい~
人が来ればお祭りは自然と盛り上がります。
人が人を呼ぶとでもいいますか、そこから何か開けたらよいなと常に思うまちこでした。
安房神社、普通に参拝に来てもご利益ありますが、お祭りの日は「縁日」といってその神社にとって特別な日。
お寺さんなんかでは、功徳が倍になる人としても知られています。
そんなご利益倍増に日に、安房神社にもいらしてください~
安房神社周辺の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)