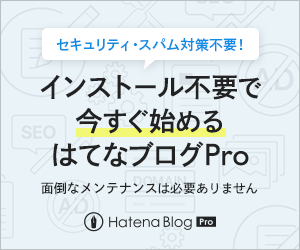こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は、江戸時代の特色を色濃く残すお祭り千葉県鴨川市「鴨川(かもがわ)」の祭礼をピックアップしました。
ではでは早速!
鴨川祭礼について
鴨川市は南房総の東側(太平洋側)にある市で、南房総の中では主要市の一つ。
鴨川シーワールドを中心に海に関する観光が盛んですが、内陸に入ると大山千枚田をはじめとする棚田や、長狭などの米どころもあり農業も盛んな地区でもあります。
古代から鴨川の中心地であったことから、歴史がある寺社やも多く大変見どころの多い市。
「鴨川祭礼」は、鴨川市の主にJR鴨川駅を周辺とした市街地の合同祭で、“鴨川地区合同祭礼(かもがわんまち)”とも言われています。
祭礼日
毎年9月第2土・日(平成11年まで13・14)に開催。
祭礼内容
鴨川地区の6つの神社から合わせて6台の山車(屋台)と6基の神輿、担ぎ屋台1基が参加します。
昭和48年頃に合同祭になりました。
南房総では珍しい三輪の山車(江戸後期)が出祭し、今ではあまりみなくなった担ぎ屋台を実際にモミサシされる姿を見ることが出来ます。
1日目鴨川小学校午後に全山車が集合し、夜には鴨川のアリーナにできたお借り屋で神輿たちは一夜を過ごし翌日ここから神輿(担ぎ屋台も)は出発。
2日目夕方鴨川駅全体集合しお囃子の競演。
参加地区
参加するのは地区というくくりでなく「講(同一の信仰をする人たちの集合)」という単位で、大浦、貝渚講、祇園講、熊若講、山王講、白幡講、諏訪講、横渚講の9講です。
江戸時代の特色に魅せられる
大浦(八雲神社)
大浦は鴨川港の直近の地区で、そのすぐ近くに八雲神社を祀ります。
鴨川水交団とも言われ、「大浦の担ぎ屋台巡行」として鴨川市無形民俗文化財文化財に指定。
大浦と川口地区の「明神講・山若講・宮本講・観音講」の屋台4台が「水交団」として統合した地区です。
現在の担ぎ屋台は昭和58年の作ですが、担ぎ屋台が初披露されたのは天保4年(1833)です。
屋台は波間に浮かぶ船を表現しており、3本の担ぎ棒で神輿の様に担ぎます。
約1トンにもなりかなり重たいのですが、さらに屋台には大太鼓と小太鼓と小太鼓叩き手2名、笛師1名が搭乗。
現在でも担ぎ屋台を実際に担いでいる地区は珍しく、神輿や屋台とは違う迫力のあるモミサシが見られます。
 安房の担ぎ屋台始まりの地区?
安房の担ぎ屋台始まりの地区?
貝渚講(八幡神社)
貝渚は鴨川漁港を囲むようにJR鴨川駅南側に位置する地区。
少し内陸に入ったあたりに鎮守の八幡神社を祀ります。
囃子屋台と神輿を所有。
現在の屋台は古い彫刻部材を再利用し、昭和56年に地元の鴨川市東の宮大工川股三喜
男によって作られました。
彫刻は後藤滝治義光によるものです。
神輿についての詳細は情報収集不足のため不明です。
祇園講(八雲神社)
大浦と同じ地区になりますが、祇園講と呼ばれています。
大正9年以降に製作された囃子屋台を所有していますが、それ以前は御船を出祭させていたようです。
脇障子は三代目後藤滝治義光で(刻銘あり)、平成2年に地元の大工鈴木敏通によって
改修が行われ現在に。
御船については版画が残されているだけで、詳細等については不明。
また白木造りの神輿を出祭させています。
ほかに「天王さま」と呼ばれる中型の神輿2基がありますが、大変保存状態がよく1基は鳳凰、もう1基は宝珠を掲げた黒塗りの神輿。
先代神輿の様なので現在担ぐことはされていません。
熊若講(熊野神社)

熊若の屋台正面
熊若講の熊野神社は横渚地区。
熊野神社を祀っています。
創建は南北朝時代ともいわれる古社で、「長狭群一の宮」であったとか。
横渚はJR鴨川駅周辺で、鴨川市内でも多くの商店街が立ち並ぶ商売の地区です。
囃子屋台を持ち、平成天皇の御大典(即位)記念に平成3年に新造。
後藤滝治義光による彫刻部材を使い、新造に際して川股三喜男が破風を手がけました。
神輿の出祭も行います。
台輪の正面に卍を飾り、神仏習合のころの名残が見られるのが特徴。

熊野神社の神輿
山王講(日枝神社)

山王講の山車正面
山王講は前原地区日枝神社から出祭する講で、前原地区は鴨川アリーナ沿いあたり。
鎮守の日枝神社は小高い丘の上に祀られています。
鴨川の祭礼には江戸型の山車が出祭します。
車輪が4輪でなく3輪という特殊な形をしているのが特徴。
人形は恵比寿様。
明治42年に神田新石町から山車を、人形を白壁町から購入し、組み合わせて使用しています。
山車自体は嘉永4年(1851)に作られたものと言われています。
その後昭和38年に初代・後藤義徳が彫刻を加え大改修が行われ、今までにも何度か改修され引き継がれています。
人形と山車はその文化的価値から、鴨川市の民俗文化財に指定されています。
山車の他に神輿も出祭させています。

日枝神社の神輿
白幡講(白幡神社)

白幡講の屋台
貝渚の中の加茂川南側に位置する川口地区白幡神社にから出祭する講で、白幡神社を祀っていることから白幡講と言われます。
文化年間(1800年初頭)に製作された囃子屋台を所有。
前破風は後藤喜三郎橘義信、後破風は太田五良平藤原政信、武志信明(伊八)の記録も残されているますが、いずれも明治期に彫刻の大きな修復が行われた様子が伺えます。
また神輿も1基所有します。
白木造りの神輿で、屋根の軒先の反りがないのが特徴。

白幡神社の神輿
諏訪講(諏訪神社)

諏訪講の山車
諏訪講は横渚の諏訪神社から出祭する講で、横渚はJR鴨川駅海岸あたりの地区になります。
鎮守の諏訪神社は、JR鴨川駅の東側に鎮座し、初代伊八の彫刻がある神社として知られています。
これを建てたのは信州(長野県)の諏訪大社の宮司で永和3年(1377)に建てられた歴史ある神社。
鴨川の祭礼には、江戸型山車と神輿が出祭。
江戸型山車は、明治43年に山王祭(東京・日枝神社)から購入したもので、江戸後期の山車と言われています。
車輪が三輪で特徴ある形をしており、購入してから何度か改修されているものの現在も引き継がれ祭礼にて曳き回しが行われていることなどから、鴨川市の有形民俗文化財に指定されています。
人形は神功皇后と八幡太郎(源頼義)で、山車同様明治期に購入、その歴史的価値から鴨川市の有形民俗文化財へ。
普段は鴨川市郷土資料館にて常設展示されています。

諏訪神社の神輿
神輿は出祭する神輿の中で一番大きく、江戸後期のものといわれています。
彫刻は波の伊八のもの。
横渚講(八雲神社)

横渚講の山車
横渚講は横渚にある八雲神社から出祭する講で、鎮守の八雲神社は鴨川イオンのすぐ隣(というより敷地内)にあります。
八雲神社の彫刻は三代伊八の彫刻が残されています。
破風山車を所有し、人形は神武天皇。
木製4輪の山車で、昭和35年ごろに製作されました。
製作者は浅草の宮本太鼓店で、人形は久月人形店より購入。
神輿も出祭しますが、神輿庫は諏訪神社にあります。
白木造りの大正のころのもの。
< 参考文献・サイト >
- 各地区の皆様!!!
- 観光/鴨川市ホームページ
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
江戸時代の特色が色濃いお祭り

鴨川市の祭礼の特徴は江戸時代の特色が、色々と残されている地区ということです。
江戸時代後期の三輪の山車。
「担ぎ屋台」は江戸時代中期にまで遡れる面白い出し物。
そしてなによりも、祭礼の参加する集団が「講(こう)」というくくりであることです。
お祭りに参加する集団は、今では地区で参加するところがほとんど。
「〇〇地区の△△」といった具合に字(あざ)で分かれて出祭することが多いですが、鴨川地区合同祭礼では「講」というくくりで出祭します。
「講(こう)」というのは簡単に言うと「同じ信仰を持つ集団」で、〇〇神社を信仰するみんなの集まり。
「字(あざ)」の場合も◇◇神社を信仰する氏子さんたちの単位でお祭りをやるので、「講」と大差ないように感じられます。
両者の決定的な違いは、地区で分かれるのではなく信仰で分かれることにあります。
なので、村や字、地区などの区切りを越えての単位になるので、隣村の人がいても全然OK。
今は名前だけが残されていることが多いので、鴨川の祭礼でも急にとなりの県から「おれは〇〇神社を信仰する同じ仲間だ!」といって来ても、早々に認められるものではないですが。
昔は村の中にはいくつもの神社やお社などが存在し、それぞれに「講」があったので、1人でいくつもの「講」に加入していたなんてこともありました。
今では地区として区画されてしまっていると思いますが、鴨川の祭礼でもいくつもの「講」に入っていたなんて人もいたようです。
鴨川市には寺社が多いと冒頭でお話ししましたが、特に房総の伊勢と言われる天津神明宮がその代表格。
天津神明宮は、伊勢神宮を本社とする天照大御神(あまてらすおおみかみ)を御祭神とする神社。
昔から伊勢神宮には「伊勢講」という全国という広いくくりでの信仰がありました。
伊勢に詣でる「お蔭参り」のためにお金を溜めて代表者が行くってものですが、鴨川には鎌倉時代から続く天津神明宮があったので、盛んに行われていたであろうことは想像にかたくありません。
しかも、江戸時代(中期以降)になると伊勢詣でがいたるところで行われていました。
この往来の中で各地の名勝をめぐり、いいものを見てきた人たちにより、南房総でも祭礼の山車や神輿などの装飾や内容が大きく変わります。
こうした流れは、第二次世界大戦後GHQによって「講」の解体があるまで続きました。
鴨川市の祭礼では、これを乗り越え現在もまだ「講」という名が残っています。
江戸後期の山車が残されている事や担ぎ屋台がめんめんと引き継がれていること、講という名称で祭礼がおこなわれていることなどなど。
鴨川は江戸時代の特色が色濃く残る地域。
そんな江戸の名残が残るお祭りはもちろん、寺社の散策はとっても面白いです。
鴨川シーワールドに来ると大渋滞しますが、この日はさらに大渋滞すると思います。
だから、ゆっくり駅前に車でも停めて、一日目はお祭り、二日目はシーワールドなんて計画がおすすめです。
鴨川は歴史があると感じてみて下さい~
鴨川の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)