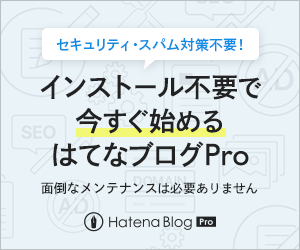こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は、安房神社ともゆかりのある神社がある地区で、歴史が古い地、千葉県南房総市「宮下(みやした)」のお祭りをピックアップしました。
ではでは早速!
宮下祭礼について
「宮下祭礼」は、南房総市旧丸山町の宮下、丸本郷、川谷地区で行われるお祭り。
平坦な田んぼばかりが広がってると思われがちですが、すぐ背後には嶺岡山系の一角に位置する山裾の地区になります。
そもそも旧丸山町は南北に海から山へ細長い町で、山間の風景と太平洋沿いの海もある自然豊かな土地です。
嶺岡の酪農や海はサーファーなどが集う自然を売りにした観光資源もある反面、南房総で一番古いお寺などを有する歴史ある地区でもあります。
南房総の古刹として知られる「石堂寺」をはじめ、館山市の安房の国一の宮である安房神社とも縁がある「沓見莫越山神社」「宮下莫越山神社」など、みどころがたくさん。
祭礼日
毎年10月10日前後の連休土日に開催されるお祭りですが、この時期は「とおかまち」と呼ばれており、宮下以外でも各地で祭礼が行われます。
なので、ひとくくりにはしていますが、宮下地区周辺で行われている祭礼の総称として「宮下祭礼」と呼ぶようになりました。
参加地区
丸本郷大畑、丸本郷上、宮下畑、宮下西根、宮下才開、宮下中、宮下吉野、宮下根方、川谷犬切、川谷鯨岡、川谷仲(川仲)、御子神の12地区。
が、まちこの情報収集不足で丸山の祭礼の区域がよくわかっていない事が多く、このうち丸本郷大畑、丸本郷上、川谷仲、川谷鯨岡、宮下中、宮下根方、御子神、宮下吉野の8地区を下記に掲載します。
引き継がれる屋台
川仲(水神社)
川仲は川谷の仲になるそうですが、詳細な場所はわかりません。
水神社を祀っています。
人形屋台を持っています。
現在のものは昭和60年頃に製作されました。
先代は昭和22年頃のもので鴨川の主基へ譲ったそうです。
鯨岡(山神社)
鯨岡は安房中央ダムの南、丸山川沿いに開けた地区になります。
山神社を祀ります。
人形屋台を所有し、現在のは昭和7年頃に製作されたもので2台目となるそうです。
中(宮下莫越山神社)
中は宮下莫越山神社を祀り、その周辺地区となります。
宮造り屋台というちょっと面白い形の屋台を所有します。
後藤滝治義光による彫刻が彫られ、現在のものは2台目です。
宮下地区の才開から昭和62年、譲り受けたものです。
先代は曳き屋台で、昭和7年頃に製作されたと言われています。
神輿は摂社の八雲神社のもので、奥宮:渡度神社と同じ渡度山にある神社です。
江戸末から明治初めの様式の神輿。
中の宮下莫越山神社は、旧同町沓見の莫越山神社と御祭神も同じで由来も同じとしますが、安房国司祭に神輿を出御させお神酒を酒造するのも沓見の莫越山神社なので、そちらが延喜式(平安時代中期に作られた法律を補う法令集みたいなもの)に記された神社という説が現在有力とされています。
 論社について
論社について
根方(?神社)
根方は宮下莫越山神社のすぐ裏手にある地区です。
鎮守はどこになるのかわかりません。
人形屋台を所有していますが、調査不足の為詳細は不明です。
御子神(王子神社)
御子神は安房中央ダムの西側になります。
王子神社を祀っています。
人形屋台を持っていて、現在のものは2台目です。
先代は担ぎ屋台であったと聞いています。
吉野(?神社)
吉野は御子神のすぐ南側の地区です。
鎮座する神社などはわかりません。
人形屋台が宮下祭礼では出祭します。
上(丸郷神社(諏訪神社))
上は宮下の南、丸本郷地区になります。
鎮守は丸郷神社です。
後藤喜三郎橘義信による人形屋台があり、亀ヶ原から購入したものと言われています。
製作年は明治25年とも。
一時祭礼を休止していましたが、昭和56年から再開し出祭するようになりました。
 亀ヶ原の祭礼
亀ヶ原の祭礼
大畑(丸郷神社(諏訪神社))
大畑も上同様丸本郷地区になります。
丸郷神社を祀りますが、現在祭礼には出祭していません。
屋台を所有していましたが、部材の一部を残し廃絶しています。
< 参考文献・サイト >
- 各地区の皆様!!!
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
歴史深いのに地元の人間は知らない

宮下地区には「宮下莫越山神社(みやしたなこしやまじんじゃ)」という神社があります。
この神社は、安房神社とゆかりが深い神社としてその歴史もとっても古い。
実は南房総旧丸山町には「莫越山神社」の名前を持つ神社が二社あります。
一つはこの「宮下莫越山神社」。
もう一つは、少し離れたところにある「沓見莫越山神社」。
両社とも1000年以上歴史を持つ由緒ある神社で、もちろん安房神社とゆかりのある神社です。
なぜ同じ名前を持った神社がこんな近くにあるのか不思議に思いますが、やはり昔の人たちも同じように思っていました。
この同じような名前、同じような場所、同じような由縁、同じような御祭神を持つ複数の神社たちのことを「論社(ろんしゃ)」といいます。
江戸時代に入ってから騒がれるようになった考え方で、どっちが本筋の神社なのかと論じることです。
どうして本筋云々という考えになったのかというと、平安時代中期に書かれた「延喜式神名帳 式内社」のせいです。
「せいです。」
というと、よくないイメージがありますが、この「延喜式」には神社のランク付けが記載されています。
だから、江戸時代に神社の整備が行われると、この「延喜式」をもとに全国の神社が一斉にランク付けされるように。
もちろん江戸時代から見ても700年以上も前に書かれたものなので、無くなっている神社や所在不明になっている神社なんかがたくさんありました。
「宮下莫越山神社」も「沓見莫越山神社」も、ランキングは上位なのに所在不明神社になってしまっていたもんだから、こっちが本物だ!あっちが偽物だ!と研究者の間で言い争いの種になってしまったんです。
「延喜式」に書かれているってことは、その神社にとってステータスみたいなもの。
そりゃどっちが本物かって話になってしまいます。
「論社」は日本全国にあり、南房総に限ったことではありません。
ちなみに、南房総にはこのほかにも、洲宮神社(館山市洲宮)と洲崎神社(館山市洲崎)、下立松原神社(南房総市旧白浜町)と下立松原神社(南房総市旧千倉町)が論社となっています。
いずれも結論には至らず、こっちじゃないかな~って感じでうやむやに現在に至っています。
そもそも1000年以上何事もなく続く神社ってのは稀で、神社内で喧嘩別れして分霊したり、地域の住民のお願いで移動したり、理由は色々あると思います。
「延喜式」に載るくらいだから、遷宮とかやっていたかもしれません。
二か所あるってことは定期的に立て替えが行われていたのかも。
通説としては、大体二社論社があると「本社」と「奥宮」としてあることが多い。
いずれにしても「延喜式」に掲載されているということは、当時の中央 と深いつながりがあったことには違いありません。
南房総には歴史がないとよくいわれます。
もちろん京都や奈良、東京など主要都市と比べたらありません。
南房総だけでなく「自分が住んでいるところに歴史なんかないない」と思っている全国各地の地元民さん。
そんなことないんです。
ただ有名じゃないから、みんな知らないだけ。
だから地道に宣伝頑張ります!
もちろんまちこが絶賛推奨中の南房総のお祭りたちも、実は歴史深い神社がたくさん。
彫刻なども見もので安房の動く美術館。
見に来て下さいね~
宮下の宿泊や遊び場情報を検索するときは、レジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)