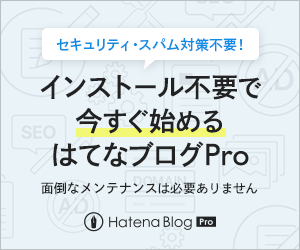こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は昔から千葉県館山市の寺町「那古(なご)」のお祭りをピックアップしました。
ではでは早速!
那古について
館山市那古地区は、古くから補陀落山那古寺の門前町として栄えていました。
この補陀落山那古寺、実はとっても歴史があるお寺なんです。
坂東三十三観音霊場第33番(結願寺)で知られ、国の重要文化財なんかもあるお寺だったります。
地元では「那古観音(なごかんのん)」といわれ親しまれています。
創建年は717年とも言われ、大変由緒あるお寺。
この那古寺を主催にした祭礼が「那古祭礼」で、毎年7月の中旬頃に開催されています。
神社を中心とした祭礼は数多くありますが、お寺を中心とした祭礼はとても珍しく、那古祭礼はその一つとして知られています。
那古祭礼について

那古祭礼の様子
祭礼日
7月中旬の土日(※本来は7/17、18)ですが、周辺で同じ時期に開催される祭礼がいくつかあるため、日にちが前後する場合があります。
参加地区
大芝、芝崎、宿、寺赤、濱、東藤の6地区です。
祭礼内容
二日間行われる祭礼は、一日目は各町内廻り、二日目は合同曳きまわしという日程です。
二日目の夜には那古寺周辺道路が歩行者天国となり、各山車・屋台がお囃子の競演があり、大変熱気あふれる時。
初日の午前中には寺主催の祭礼の通り、那古寺で安全祈願の護摩供法要が行われます。
いつ行っても神社の祭礼とは違った雰囲気を楽しめます!
館山市の文化財に指定されている山車もある
大芝

大芝山車全体写真
明治30年より那古寺の縁日に併せて祭礼を行うようになり、大芝はその最初のメンバーに一つでした。
それ以前より山車を持っており、現在のものは明治11年に館山市北条から購入したものと言われています。
人形は「神武天皇」で昭和61年に制作されました。
同じ年に幕も新調されています。
三層の山車の内部に格納されていますが、必要に応じて最上部にまで上げることが出来ます。
彫刻師は後藤喜三郎義信。
 大芝の詳細はこちら
大芝の詳細はこちら
柴崎

柴崎山車全体写真
柴崎の山車は東藤と同じ時期に作られ、那古地区では一番早く山車を所持してい地区です。
各町それぞれで行われていた祭礼を、明治30年の合同祭にしその時から参加しているメンバーでもあります。
山車の骨組みは明治30年以前に作られており、鳳凰は昭和初期に彫刻師の後藤義房が彫刻しています。
他、後藤喜三郎橘義信も携わっていると言われています。
人形は「天照大神」で昭和6年に制作されていますが、それ以前は「素戔鳴命」でした。
三層の山車の中に格納され、必要に応じで上下させることができます。
昭和6年に地元棟梁関万次郎が山車を改修し、その年に幕も新調されています。
 芝崎の詳細はこちら
芝崎の詳細はこちら
志久

志久屋台全体写真
宿はもともと那古寺の合同祭には参加しておらず、大正12年にはじめて参加するようになりました。
現在は人形屋台ですが、先代は踊り屋台で新調時に国分に売却したと言われています。
大正4年に地元棟梁中村仙太郎が制作し、後藤喜三郎橘義信が彫った彫刻が屋台破風部分にあります。
 宿の詳細はこちら
宿の詳細はこちら
 国分のお祭りを見てみる
国分のお祭りを見てみる
寺赤(閼伽井弁天)

寺赤山車全体写真
寺赤はもともと那古寺の裏参道にある閼伽井弁天を祀った祭礼をしていましたが、明治34年に参加するようになりました。
明治32年に造られた寺赤の山車は、2003年に館山市の指定有形民俗文化財に指定されています。
山車全体が「太平記」を表現しており、人形も「後醍醐天皇」幕は「楠正成」と各名場面を見ることが出来ます。
彫刻師後藤利兵衛橘義光晩年の最高傑作とも言われており、山車の文化財的はとても高いです。
また、明治43年に制作された幕は100年近く経っていたため、平成13年9月に改修され美しい姿を取り戻しています。
 寺赤の詳細はこちら
寺赤の詳細はこちら
濱(厳島神社)

濱山車全体写真
濱は仲濱と大濱の二つの区から成り立っており、那古の海岸線に位置する地区です。
厳島神社を祀っており、山車の全体的なイメージも厳島神社の御祭神「弁財天」となっています。
人形はもちろん「弁財天」で、昭和60年幕と一緒に京都にて製作されました。
現在の山車は2台目で、明治43年に地元棟梁山口仙太郎が製作。
先代は川名から購入しその後国分へ譲渡されました。
この時の幕と人形は大正10年に作られたものと言われています。
彫刻師後藤喜三郎橘義信で、彫刻も安芸の宮島や厳島神社が彫られています。
平成16年5月に大改修が行われています。
 濱の詳細はこちら
濱の詳細はこちら
 川名とはどこ?
川名とはどこ?
東藤(白岩弁財天社)

東藤山車全体写真
東藤は補陀洛山那古寺の御膝元であり、白岩弁財天社を祀る地区です。
那古地区で最初に山車を製作した地区でもあり、現在のものは6代目です。
それまでは花車であったり、屋台であったりと様々な形の山車をもっていたようです。
山車は、人形の「豊臣秀吉」を筆頭に「太閤秀吉の出世物語」をイメージして作られています。
昭和11年に東京人形師浪花屋七郎兵衛によって人形を、東京刺繍師内田宗一によって幕が作られました。
山車も昭和11年に地元大工加藤在一郎が製作し、彫刻師後藤家の初代後藤義徳が彫っています。
 東藤の詳細はこちら
東藤の詳細はこちら
その他参加する祭礼
各地区とも那古祭礼の他に、南総里見祭りに参加することがあるます。
参加はしたりしなかったりその年によって違いますので、詳細については一般社団法人館山市観光協会の案内を参考にしてください。
< 参考文献・サイト >
- 南房総 花海街道
- 各地区の皆様!!!
- ちば南房総「安房国札観音霊場巡り」
- 館山市役所のホームページ
珍しい寺の祭り~まとめ~
日本のお祭りは神道系のもの、つまり神社が中心となる祭礼がほとんど。
でも、日本各地を見ると寺を中心とした祭礼は実はいくつも存在します。
千葉県では、成田山新勝寺と補陀落山那古寺が寺を中心とした祭礼として知られています。
祭礼する意図や内容はほぼ同じなのですが、神社の様に神主さんが祝詞を唱えるのと違い、お寺なのでお坊さんが安全祈願の祈祷などを行います。
普通のお祭りのイメージでいると、ちょっと不思議な感覚。
門前町で栄えた町ならではの祭礼と言えます。
また、那古寺は里見氏と大変関係が深く、安房の古刹の一つでもあります。
そのため、館山市鶴谷八幡宮(安房の総社)の別当寺(神社の管理や統括を行うお寺の事)として、安房国司祭にも参加していました。
このときもお寺の開催する放生会としてお祭りを仕切っていたと言われています。
今でも、補陀落山那古寺にはたくさんの人が観光、御朱印をもらいにやって来ます。
富浦インターから降りて、ちょっと中に入った場所にあるのですが、駐車場も完備されていますし、御朱印も随時受け付けているので、大変行きやすいお寺です。
ただ、こちらの地区もいわずもがな少子高齢化進んでます。
食べるところ泊まるところは、館山市街地までいかないとちょっと大変かもしれません。
それに市指定の文化財とはいえ、山車の迫力は一見の価値があります。
彫刻すごいんです。
また、大人だけでなく出店も那古寺に出ていますので、お子さん連れでも楽しめます。
すぐ近くの那古海岸は海水浴場としては穴場なので、そこに遊びに来ながらお祭り観覧ってのもおつかな!
海水浴に来たら、お祭り見てください~
地元の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)