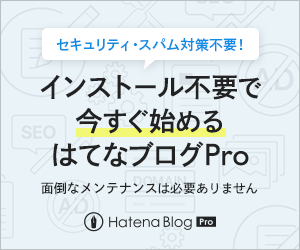こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は、かつては鴨川市でも絢爛豪華な屋台が出祭していたことで知られる千葉県鴨川市「田原(たばら)」のお祭りをピックアップしました。
ではでは早速!
田原祭礼について
鴨川市街地を抜け、長狭街道入口から鴨川有料道路金山ダム周辺の地区を「田原(たばら)」といいます。
道沿いの細長い地区で、昔から農業が盛んで、現在も兼業農家の方が多いのが特徴。
この田原地区で行われるのが「田原祭礼」で、神楽(獅子舞)なども行われる昔ながらの祭礼を行っている地区でもあります。
祭礼内容
波の伊八の出身地である打墨(うっつみ)にも近いことから、伊八の彫刻はもちろん安房を代表する彫刻師:後藤一派の作品を数多く残す祭礼でもあります。
 伊八の故郷、打墨の祭礼
伊八の故郷、打墨の祭礼
が
大変残念なことに、とてつもなく過疎化が進んでいます。
廃絶した屋台なども何地区かあり、内容が不明な地区も多々。
中でもこの地区の一つである、太田学。
鴨川市内でも豪華な屋台があったこととして知られていたものの現在はお祭り自体も休止中。
さらには解体して保管していた屋台は、彫刻の一部が盗難にあったりし完全な形で残されていません。
ほかにも同じような地区があります。
代々伊八による彫刻があった屋台が多数あり、不明なものも考えると貴重なものもたくさん。
また、この田原祭礼と同日に行われる獅子舞「川代神楽」は、江戸初期から引き継がれるもの。
こちらも担い手不足で、絶賛廃絶の危機。
だから、早く行かないと見る機会はどんどん減る可能性があります。
こりゃ行くしかありません。
祭礼日
田原祭礼は毎年9月の第4土日で、川代神楽は日曜日に奉納。
参加地区
池田、川代、竹平の3地区。
近隣の地区もこちらのページに掲載中。
金山、日摺間、太田学、坂東、押切、京田、太尾、来秀、大里、田原西も見てください。
波の伊八の美術館
池田(愛宕神社)
池田は長狭街道を入って、田原小学校を少し過ぎたあたりの地区。
愛宕神社を祀ります。
4代・伊八信明の彫刻による囃子屋台を所有。
明治33年に製され、平成7年に川俣三喜男が改修を行っています。
川代(須賀神社)
川代は田原小学校や鴨川総合運動場の裏手に広がる地区。
その中の住宅街に須賀神社を祀っています。
須賀神社では囃子屋台と神輿を出祭。
屋台は5代伊八高石信月の作品を見ることが出来ます。
大正5年に製作されたもので、平成8年頃改修。
神輿は文化3年(1806)のものとされますが、大変きれいでこまめに修復されていることが記録などからもわかっています。
川代にあるもう一つの熊野神社とともに、川代神楽を奉納。
江戸時代初期から伝わっているものです。高齢化や少子化、過疎化の影響で、伝承に困難をきたしているそうです。
川代(熊野神社)
川代は田原小学校裏手にあたる地区。
熊野神社は山間にある神社です。
神輿と宮立てがあるそうです。
詳細については調査中の不明です。
川代には熊野神社と須賀神社がありますが、この二つの神社で奉納されるのが川代神楽と呼ばれる神楽です。
始まりは江戸時代初期と伝えられ江戸の町神楽と同系列のものとされます。
戦時中欠かさず奉納されてきたていますが、やはり高齢化や少子化、過疎化の影響で、伝承に困難をきたしているそうです。
竹平(愛宕神社)
竹平は田原交差点から千葉県道181号線を挟んだところにあります。
明治22年以前に製作された囃子屋台が出祭。
4代・伊八信明神輿もありますが、昭和40年ごろから休止中とのことです。
昭和初期に天津の浜荻から譲り受けた神輿と聞いています。
 天津の浜荻のお祭り
天津の浜荻のお祭り
坂東(愛宕神社)
千葉県道181号線、田原小学校周辺の地区。
明治44年に旧田原村の村社など10社を合祀した神社、愛宕神社を祀ります。
現在は担ぎ手不足でほとんど渡御はないそうです。
坂東(八幡神社)
上愛宕神社と同地区、千葉県道181号線、田原小学校周辺の地区。
こちらも神輿があるそうですが、現在担ぎ手不足の為出祭していないようです。
金山(?神社)
金山は鴨川有料道路を進んで金山ダム周辺の地域になります。
現在は祭礼には参加していませんが、花万燈があったそうです。
保管が悪かったためか廃絶されています。
日摺間(?神社)
日摺間(ひしま)は鴨川有料道路入口あたりの地区。
花万燈がありましたが、昭和25~40年に巡行しその後廃絶してしまったそうです。
現在も祭礼は行われていません。
太田学(?神社)
太田学(おだがく)は鴨川有料道路を挟むように左右に広がる地区です。
鴨川市の最北端で君津市と隣接します。
明治33年に製作された屋台を持っていたそうですが、現在は解体し保管され出祭はしていません。
後藤利兵衛橘義光による彫刻で、鴨川市では豪華屋台として知られていたそうです。
昭和34年から休止され、解体された後彫刻の一部は盗難などにより散逸しており、残念な状況となっています。
< 参考文献・サイト >
- 各地区の皆様!!!
- 観光/鴨川市ホームページ
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
お祭りは美術鑑賞に最高

文化財の指定を受けていないから、無名のお祭りなんか見に来ない?
それはとってももったいない。
この田原祭礼もお祭り自体は、なんの指定も受けていません。
でも、これだって立派な文化財。
田原地区のように過疎化の影響でお祭りを維持できなくなっているところは全国各地にあります。
年を追うごとに、きっとお祭りを観る機会は減って行きます。
きっと、これからどんどんなくなっていきます。
それはなにも人手不足による原因ばかりではありません。
地震や火災などの自然災害、人災(壊してしまったなど)など理由はさまざま。
例えば盗難もその一つ。
最近、日本の文化財のみならず世界中で文化財の盗難売買が行われ深刻な事態とないます。
田原地区のように、無指定のものは資料等が少なく把握しきれず、もし盗難され売買されても、発覚せずそのままうやむやになってしまうことがほとんど。
しかも海外でそれをやられると、多分跡を追うことはほぼ不可能。
全国区で知られているわけでもないし、地元民でもあまり知っていませんが、南房総にはたくさんの価値のある山車や神輿、寺社があります。
もちろん無指定のものがたくさん。
だいたい外に野ざらしだったり、山車小屋がぽつんとあったりして、すごく狙われやすい。
戸締りはもちろん、神社などで所蔵するもの(外にある狛犬とか石造のものなんかも全て含む)の目録帳や、写真などで特徴を記録しておくなどが大事だったりします。
例えば、神輿だったら地区で詳細な写真を撮って保管しておくなど。
国宝とか重要文化財の話だろう、こんな片田舎のものを盗む奴なんかいないだろうってのはないのです。
世の中にはいろんな人がいます。
⇒文化財の防犯対策について (平成22年4月26日 22庁財第139号) | 文化庁参考にしてください。
最近有名になってきた伊八の作品は狙われやすいそうで、お寺によっては拝観禁止になったり撮影禁止などがされているところが結構あります。
有名になることはとてもうれしいことですが、その分悩みも増えます。
また、世界的にも文化財を守る条約が出来ています。
どこに行っても悪質な行為は罰せられます。
ちなみに文化財を盗んで、窃盗罪として有罪判決になったら、刑罰は10年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、これに文化財保護法などの特例が付くのでもっと重たくなる可能性が。
盗みを働く人のことを前提に色々考えるのは悲しいですが、こうした人たちによって、または自然災害などによって、結構あっけなく文化財は姿を消します。
だから、今見にいくしかない。
日々の旅行としてお寺や神社に行くのはもちろんですが、お祭りのように1年に1回とか何年に1回とかいう貴重な体験を逃すのは、とってももったいない。
お祭りはそうした貴重な無名の文化財たちにも出会える最高の日です。
鴨川市だけでなく南房総には伊八の彫刻が残された神輿や山車がたくさんあります。
さながら、伊八の美術館。
現在伊八の美術館なるものは存在しません。
貴重な伊八の作品を見たいならお祭りに行くなどしか方法がない。
なので、伊八の動く美術館だと思って、足を運でみてくださいね~
田原の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)