こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は千葉県館山市の城下町として栄えた「館山(ふなかた)」のお祭りをピックアップしました。
城下町というだけあって、煌びやかで他のお祭りとはやっぱり一線を画す魅力がある。
ではでは早速!
館山祭礼について

館山人神社正面から見た様子
館山は千葉県南部に位置し、今回ご紹介する館山祭礼の地区はその経済や文化の中心として栄えた町です。
古代から条理制(土地区画の制度)が敷かれ、中央の朝廷とも密接に関係を持っていました。
中世以降は里見氏の支配地とされ、館山城が出来てからは城下町として発展しますます経済や文化がここを起点に安房の各地へ。
港もあり、戦時中は軍都とされ現在も館山航空隊(海上自衛隊)があるなど、その遺構がいたるところに残されています。*1
この館山の中心、館山城のすぐ下に館山神社があります。
関東大震災で倒壊してしまった各地区の神社が合祀され、「館山祭礼」はこの館山神社を中心とした各社の合同祭で、大々的に行われている規模の大きな祭礼。
「たてやまんまち」とも言われ、合同祭が始まり約100年経ちます。
祭礼日
もともと各神社各地区で行われていた例祭を大正3年旧館山町と旧豊津村の合併をきっかけに大正7年より8月1、2日に祭礼を合同で行うようになったそうです。
参加地区
13地区8社の合同祭礼として行われ、神輿7基、曳舟2基、山車4基が出祭。
新井、下町、仲町、上町、楠見、上須賀、大賀、笠名、宮城、沼、上真倉、青柳、柏崎の13地区。
祭礼内容
二日間行われる祭礼は、初日に各町内を廻り、2日目は館山神社境内と周辺に山車や御船、神輿が集まります。
両日とも館山神社前の道路が夕方ころ歩行者天国となり、多くの人で賑わいます。
各山車の人形の披露やお囃子の競演はその山車や御船の数と併せ圧倒されます。
また神輿のモミサシも見られ、祭礼の見どころがギュッと詰まった2日間です。
館山神社を中心に行われる館山の顔となる祭礼でもあります。
山車・御船・神輿の数に圧巻!
お囃子の音に聞き惚れる
新井(館山神社(諏訪神社))

新井「明神丸」正面(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
館山市の中央に位置し、海から内陸にかけての細長い区域です。
もともと地区内に諏訪神社が鎮座していましたが、大正12年関東大震災を機に昭和7年5月館山神社への合祀となりました。
新井地区が有する御船「明神丸」は朱塗り漆の御船で、後藤喜三郎橘義信が手掛けた彫刻が船をきらびやかに飾っています。
明治27年に作られたものと言われ、その後小規模な改修を経て平成5年に大改修が行われました。
先代の御船は江戸時代に地元の船大工が製作したと言われていますが、詳細は不明です。
祭礼の際に歌われる「御船歌」は「新井の御船歌(あらいのおふなうた)」と言われ、館山市の無形民俗文化財に平成20年に指定されています。
上演される内容等については以下をご参考下さい。
現在伝わる御船歌には、
①「木更津(きさらぎ)山」
②「是(これ)のつぼね」
③「初はる」
④ 「桜くどき」
⑤「鳴戸舟」
⑥「真鶴くどき」がありますが、上演されるのは主として①と②です。
曲の長さや内容が手ごろだということがその理由です。
例年2月下旬の新年会では、歌い初めとして①を歌うことになっています。
③も以前は歌われていましたが、長いので最近は上演されていません。
8月の祭礼時、御船山車巡行に際して、上演される場所と歌は次の通りです。
8月1日:集会所・①、新釜旅館前・②、区長宅前・②、集会所・①
8月2日:集会所・①、館山神社・①、お浜入り・②、さくらや旅館前・②
下町(館山神社(諏訪神社))

下町の山車(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
下町は、館山地区の最東部に位置し汐入川沿いの地区。
諏訪神社を祀っていましたが、関東大震災で倒壊したため昭和7年5月館山神社への合祀され現在に至ります。
明治24年11月に作られた下町の山車には、伊邪那美命(いざなみのみこと)が飾られています。
普段は山車に格納されていますが、館山神社で全身を見れる。
昭和34年、56年、平成14年に改修。
後藤喜三郎橘義信の彫刻で、上部の三連の彫刻は大変見物です。
下町には昔から「きつね踊り」が伝わっており、山車にきつねの面をつけた人間が乗っている時があります。
きつね踊りが披露されるのは1日目の夜で、青柳、上真倉との神輿との共演も見られます。
 下町の写真はこちらで多数掲載中
下町の写真はこちらで多数掲載中
仲町(館山神社(諏訪神社))

仲町の山車(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
仲町は館山城下通り沿いに位置します。
館山城下麓にある公園は、仲町の諏訪神社が鎮座いしていた場所でしたが、関東大震災の際に倒壊してしまいました。
そのため昭和7年に館山神社へと他の地区の神社とともに合祀。
仲町の山車は、明治二十八年に地元大工の吉田竹次郎によって製作。
彫刻は後藤喜三郎橘義信で、人形は下町の伊弉冉尊(いざなみのみこと)ととの夫婦神である伊弉諾尊(いざなぎのみこと)です。
人形は電線の関係などで通常は山車内部に格納されていますが、館山神社に集合した際には全身を見ることが出来ます。
平成9年に大改修が行われ、平成25年には幕が新調されています。
仲町が得意とする踊りを披露するために、お囃子座が広く設けられているのが特徴です。
また、仲町の倒壊してしまった諏訪神社には、安房の名工・武志流三代目武志伊八郎信作の龍がありました。
今は、別当寺の長福寺堂内に他の彫刻と共に保存されています。
上町(館山神社(諏訪神社))

上町の山車(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
上町は館山城下から海岸へ延びる区域で、諏訪神社が鎮座していました。
しかし、関東大震災の際に倒壊してしまったため、同じく倒壊してしまった他の地区と話し合い館山神社に合祀される事になったそうです。
明治中頃に製作された山車は、昭和54年に山車の大々的な修理が行われ、併せて幕の新調を行いました。
下町と山車を交換したという話もありますが定かではありません。
彫刻は山車彫刻としては珍しい後藤秀吉橘義雄の作です。
人形は「国常立尊(クニトコタチノミコト)」で、館山神社に他地区とともに集合した時に全身を見ることが出来ます。
倒壊してしまった諏訪神社には武志伊八郎信美作の龍が彫刻されていました。
今は上町の集会所に大切に保存されています。
ちなみに上町の山車は以前は祭礼の度に組み立てていただんだとか!
 上町の山車をもっと見たい方はこちらの記事へ
上町の山車をもっと見たい方はこちらの記事へ
楠見(館山神社(厳島神社))

楠見の山車(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
楠見は館山城下すぐしたの地区になります。
厳島神社を祀っていましたが、他地区同様関東大震災により倒壊してしまったため館山神社へ合祀されました。
山車は後藤喜三郎橘義信の彫刻で飾られ、 昭和56年から平成29年に至るまで複数回の修復、幕などの新調が行われています。
人形の「仁徳天皇」は館山神社に他地区と集合した際に全身が見れます。
楠見は「天狗舞」が有名。
2日間で6回、楠見の踊りをみることができます。
上須賀(館山神社(八坂神社))

上須賀の神輿(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
上須賀は館山城を含む館山地区で最も広い地区です。
八坂神社を祀っていましたが、関東大震災の倒壊を機に他地区と併せて館山神社に合祀されました。
神輿を有し、明治29年に地元の大工や塗師などによって作られ、何度かの大改修を経て平成8年に百年奉納祭も行われた歴史ある神輿でもあります。
特徴は神輿の屋根四面に飾られている「吹き替えし彫刻」で、後藤福太郎橘義道作と言われています。
また、彫刻師は義道以外に初代後藤利兵衛橘義光、三代目後藤義光も手掛けており、大変見どころの多い神輿と言えます。
この神輿に負けぬ優美な子供神輿もあり、祭礼の親子神輿の競演は見どころの一つとなっています。
大賀(御瀧神社)
大賀は館山地区の最も西側に位置します。
海側の地区に相応しく、水の神を祭神とする御瀧神社を祀っています。
総白木作りの神輿は平成20年に完成した新しいものですが、御瀧神社にちなみ随所に龍の彫刻がふんだんに施され大変美しい神輿です。
館山の祭礼に参加する神輿はほとんどが館山神社(上須賀)のものと似ていて、大賀の神輿も発注の際に館山神社と同じ形にするようにしたとか。
笠名(神明神社)

笠名の神輿(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
海側の海上自衛隊の近くにある笠名は、神明神社を祀る地区です。
嘉保年間(1094~1095)に國司神社の祭神でもある国司:源親元が伊勢神宮の遥拝所として勧請したことが始まりとされる神社です。
神輿を有しますが、現在の神輿は2代目で昭和5年地元の大工(里見氏に仕えた宮大工といわれている)の手によって作られました。
彫刻は三代目後藤義光によって彫られました。
当初は白木作りの神輿でしたが、平成15年の修復で黒塗りになったそうです。
初代の神輿も黒塗りあったと言われており大変重たい神輿で、曽呂村西神社へ売却されたと言われていますが定かではありません。
神輿を豪快に動かすことで知られており、館山祭礼の見どころとなっています。
宮城(熊野神社)

宮城の神輿(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
館山地区の西側少し内陸に入ったあたりにある宮城は、熊野神社を祀ります。
大正4年に作られた神輿は幾度の修復を経て、現在も白木作りをの美しい姿を保っています。
後藤源義定によって手がけられた彫刻は白木造りの神輿にとても映え美しい姿を見ることが出来ます。
沼(天満神社)

沼の神輿(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
沼は館山地区西側に位置し、菅原道真を御祭神とする天満神社を祀っています。
嘉保2年(1095)、國司神社の祭神である安房国司:源親元の創立と伝わる神社。
館山地区で最も大きいとされる神輿には、菅原道真公梅鉢が紋として掲げられ、後藤義光によって彫られた彫刻が更に重厚感を表しています。
館山の祭礼で出祭する神輿の中で一番大きい。
祭礼の時には、神輿の重さを感じさせないモミサシが見どころです。
上真倉(神明神社)

上真倉の神輿(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
館山地区の東端にある上真倉は、広い農業地域を有します。
神明神社を祀り、世帯数も館山地区で最も多い地区でもあります。
この神明神社は建長元年(1249)に郡司安西孫八郎が安房4群の伊勢神宮の崇拝宮として勧請したことがはじまりとされます。
白木造りの神輿を持っており、その白さを維持するために定期的な改修を行っています。
先代の神輿は明治31年、今の神輿は平成17年作。
また上真倉の神輿には四方ににらみを効かせる4匹の狛犬が彫られていますが、他の神輿に比べてこれが大きいのが特徴です。
初代後藤義光によって作られた彫刻は、「牛若丸と弁慶」にちなんだものが飾られています。
青柳(日枝神社)

青柳の神輿(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
青柳は館山地区の東側、館山バイパスの辺りにあります。
鏡ヶ浦を臨める高台に日枝神社が鎮座します。
大神輿(おおでん)と小神輿(こでん)と言われる二つの神輿があります。
大神輿は、赤と黒の漆で塗られ細かな部分に色鮮やかな彩色がされており、鮮やかな風合いを醸し出しています。
初代後藤利兵衛橘義光によって手がけられた彫刻は、太平記を題材に彫られた見事なものです。
明治31年に地元の大工や錺師によって製作されいます。
青柳は、子供たちを中心に、お浜入り、館山神社神輿入祭の際に奉納される鞨鼓舞をする役目を担っています。
上真倉の神輿と一緒に行動することが多いです。
柏崎(國司神社)

柏崎の「國司丸」(写真は里見祭りの時に撮影したもの)
館山港の辺りに位置する柏崎には、平安時代にまで遡ると言われる國司神社が鎮座します。
御祭神である源 親元は、安房の国司として京から赴任してきた人物で、この地で数々の善行を行ったと伝えらています。
任務完了に際して柏崎より船で帰路に就きましたが、その後親元の死を知ったこの地区の人々がその死を惜しみ國司神社のもととなる小洞を作ったのがはじめと言われています。
大変古い歴史を持つ「國司丸」という御船があります。
左側の艫の支柱に文化14年の墨書があり、その制作年は文化7年とも言われています。
現在の御船は昭和8年、32年、平成9年に改修をし、当時の部材はほとんど残っていませんが、御船の形は古いもので大変貴重なものです。
後藤福太郎橘義道、後藤滝治義光によって彫られた彫刻が國司丸を飾ります。
新井の御船歌と同様、柏崎も平成20年館山市無形民俗文化財に「柏崎の御船歌」(かしわざきのおふなうた)が登録されています。
1月16日の柏崎のオビシャと、8月1、2日に行われる國司神社の祭礼(館山祭礼)の際に聞く事が出来ます。
上演内容等は以下をご参考下さい。
歌は「國司丸船歌」と呼ばれる祝い歌に始まり、「皇帝」、「正月くどき」(2種)、「初春」(2種)、「鹿島くどき」、「八幡くどき」、「道中くどき」、「四季」、「西の宮」、「入船紀州祝いの谷」が伝えられいます。
しかし現在は、正月のオビシャの時に「國司丸船歌」と「正月くどき」が、8月の祭りには「國司丸船歌」と「皇帝」のみが歌われています。
國司神社の祭礼には、御船山車の曳き回しが行われ、お囃子(サンギリとバカバヤシ)を演じた後、御船歌とお囃子が組み合わされて奉納されます。
祭礼時の御船歌はヨミヤ(宵宮)である8月1日の夜、國司神社の前で奉納され、2日には出発場所である國司神社前で演じられた後、沼・柏崎から宮城の熊野神社、笠名の神明神社、大賀の御滝神社の前で奉納されます。
 國司丸の写真をもっと見たい方はこちらの記事へ
國司丸の写真をもっと見たい方はこちらの記事へ
その他参加する祭礼
各地区とも館山祭礼の他に、南総里見祭りに参加することがあるます。
その年によって参加する地区が異なります。
詳細については一般社団法人館山市観光協会の案内を参考にしてください。
< 参考文献・サイト >
- 南房総 花海街道
- 各地区の皆様!!!
- 館山市役所のホームページ
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
館山市の歴史は意外に長い~まとめ~
館山の観光はもっぱら「海」を売りにしています。
というか、南房総全般。
もちろん、それもそうなんですが、もう少し色々なものを売りに出そうじゃありませんか。
というわけで、まちこは「お祭り」を絶賛推奨中です。
中にいる房州人もぶっちゃけ「館山ってなにもないところ」と思っている人が多く、かくいうわたしもその一人。いやいやすいません。
こちらの館山祭礼は、臨時駐車場も出来るほど。
車で来ても、電車で来ても館山駅の近くなので安心して下さい。
出店も楽しいよ。
館山の観光ですが、彫刻散策ってのもおすすめ。
例えば、突然ですが日光東照宮のあの建築の彫刻をした人たちってあのあとどうしたか知っていますか?
江戸を中心に活躍していたのですが、そこに見習いに行っていた地方の人間がたくさんいるんです。
その中に、現在の館山の寺社建築や神輿、山車の彫刻のほとんどを手掛けていた後藤一派があります。
系譜をたどれば、あの眠り猫の左甚五郎まで行き着く人たちです。
波の伊八は有名ですが、こちらの後藤一派も有名ではないけれどたくさんの作品を残しています。
南房総のいたるところに彫刻が残されています。
スケールを大きくすると「日光東照宮の彫師の末裔たち!」みたいな宣伝も出来る訳です。
これはちょっと言い過ぎかもしれませんが、かつて中心地となった東京が戦中の大空襲で、遺作が大分少ないんです。
その系譜を継いでいる作品は現在関東のローカル地方に数多く点在しているという。
だから、関東のローカル地方のみなさん。
あなたのその町、宝がたくさんありますよ。
神社のその彫刻、もしかしたらすごいお宝になるかも。
館山って海だけじゃないのか~、実は芸術の都?(笑)くらいに感じてもらえるとありがたいです。
実は歴史はちゃんとある。
それに「おらがまち」にも「房州弁」でいらしてくれる人がいますが、生で聞くならお祭りがおすすめ。
みなさんが来てくれる一押し記事は「房総の方言「房州弁」」です!
なぜなら、なんだか妙にお祭りに合う口調なのです。
お祭りの練り歩きの最中に「木遣り(きやり)」という歌を歌いますが、聞いていて「おお房州人」って納得していまうこと請け合いです。
決して口調が荒いからと房州人はヤンキーではありません。
関西の方たちは喧嘩売られてると思うようですが、そんな度胸もありません。
あばら一本足らない房州人の大らかさをお祭りで感じてもらえたらなぁ。
だから一度はお祭り見に来てください~
館山の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)
あなたも自分の地元のお祭りをネットで情報発信してみませんか?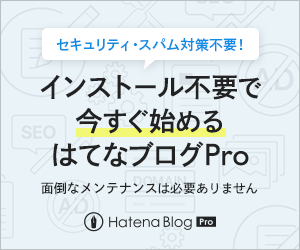
同志たちよいざ行かん!
*1:赤山地下壕跡が有名