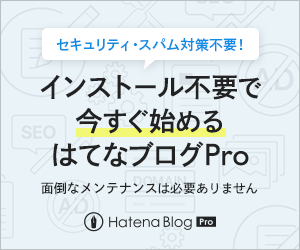こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は、千葉県下最古の温泉がある千葉県鴨川市「曽呂(そろ)」のお祭りをピックアップしました。
ではでは早速!
曽呂祭礼について
曽呂地区は嶺岡山系の南側で、曽呂川に沿って東西に伸びる道にある地区。
昔は仏閣などが多く僧侶がたくさんいたことから「曽呂」と呼ばれるようになったとか。
農業中心の地区ですが、すぐ近くの嶺岡山系では古来より牧場が培われた地で、江戸時代に徳川吉宗により白牛がインドから輸入されここで飼育をされるようになりました。
日本酪農の発祥の地とされ、「千葉県酪農のさと」では白牛や羊・ヤギなどが放牧され、周辺でも搾乳のため牛を飼育している農家があるところ。
そのため牛に関わる祭礼行事も。
全国的にも珍しい「牛洗い行事」というものです。
「代」の八雲神社に安置されている陶製の白牛(40センチほど)を曽呂川まで連れて行き身を清めるという行事。
古くから家畜に触れてきたことから、この牛を洗う事で家畜の無病息災や五穀豊穣を祈願したことが始まりといわれています。
毎年6月のはじめに行われます。
また、曽呂温泉は千葉県では最も古くから営業している温泉として知られています。
黒い湯が出てお肌つるつるになるんだとか。
気になった方。
曽呂の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
祭礼日
曽呂祭礼は10月体育の日連休の中日曜(昔は9日)に開催。
祭礼内容
統一行動等はなく、それぞれの神社で同じ日にお祭りを開催。
鴨川市でよく見られる宮立てや、それぞれの神社で行われる神事(獅子舞等)など古くからの農村の形の祭礼の姿を見ることが出来ます。
参加地区
上、代、仲、二子、宮、東の6地区。
西、畑については休止中、東については詳細が不明。
山間の農村の古式ゆかしい行事
上(八雲神社)
上は鴨川市街地を南へ抜け、曽呂十字路を山間に入ってしばらく行くとある地区。
八雲神社を祀ります。
囃子屋台を所有。
後藤滝治義光による彫刻で、曽呂地区の上の佐粧勇治が昭和4年に製作しました。
代(八雲神社)
代は曽呂十字路を山間に入ってすぐの地区です。
八雲神社(上とはまた別)が鎮座。
囃子屋台を所有し、彫刻を石井半兵衛、林清吉・座間平吉が安政3年(1856)に製作。
平成12年には畠山靖弘によってが改修が行われています。
さらに神輿1基所有。
仲町(奥野神社)
仲町は曽呂十字路を山間に入ってから、道が分岐するあたりの地区。
鎮守の奥野神社は御祭神が長狭姫命といって、長狭国造との関連が伺え創建年代は不明なものの時代はかなり遡れるのではないかと思われます。
囃子屋台を出祭させています。
昭和4年に曽呂地区の上から譲り受けたもの。
さらに神輿1基所有。
西(西神社)
西は曽呂十字路を山間に進み、鴨川市と南房総市旧和田町との境にあります。
西神社を祀っています。
御祭神が大山祗命(おおやまつみのみこと)から日枝神社系列の神社。
明治24年後藤喜三郎橘義信による彫刻の屋台を所有していますが、現在は休止中。
神輿は、館山市笠名の神明神社初代神輿。
2018年のたてやまんまち100年祭に、90年振りに里帰りしお披露目がありました。
畑(熊野神社)
畑も西のすぐ下の地区で、南房総市旧和田町との境にあります。
熊野神社を祀ります。
囃子屋台1・神輿1基・宮立1基を所有していますが、現在は休止中で神事のみが執り行われています。
屋台は昭和3年に江見の石井治郎吉が製作し、後藤滝治義光による彫刻が彫られています。
東(東神社)
東は曽呂十字路から山に入って曽呂地区の真ん中あたりの地区になります。
東神社が鎮座。
御祭神を大山祗命(おおやまつみのみこと)としていることから、日枝神社系の神社のようです。
屋台を持っているようですが、詳細についてはわかりません。
現在休止中です。
二子(石尊神社)
二子は曽呂十字路から千葉県道89号線から一本中に入った、田原地区と境にある地区。
石尊神社が祀られています。
大山祗命(おおやまつみのみこと)が御祭神なので、日枝神社系の神社。
囃子屋台が出祭。
昭和3年ごろに地元大工の松本善治が製作したもので、彫刻には松本勲、鈴木政吉の銘も残されています。
宮(東宮神社)
宮は曽呂十字路を入ってすぐの地区。
東宮神社を祀っています。
御祭神が二柱(瓊々杵命(ににぎのみこと)、木花之開耶比賣命(このはなさくやひめのみこと))なので、浅間神社系のもの。
夫婦神なのですが、どちらかというと木花之開耶比賣命が主祭神。
囃子屋台と神輿2基所有。
屋台は後藤利兵衛橘義光による彫刻で、明治16年に製作されたものです。
神輿2基の渡御はなく、祭礼当日に飾るのみ。
< 参考文献・サイト・情報提供 >
- 西川隼様
- 各地区の皆様!!!
- 観光/鴨川市ホームページ
日本の農村のお祭りは見に行きづらい・・・

現在「お祭り」というと、都市部を中心としたワイワイと賑わう大きなイベントのようにとらわれがちですが、本来お祭りというものは「村」という団体で行われる神聖な儀式の一つでした。
出店や露店、山車の曳き回し、神輿のモミサシがメインになっていないお祭りに人出はあまりなく、こうした小さな農村部のお祭りは見過ごされがちです。
日本の古来から農村で行われている祭礼は、どっちゃんがっちゃんやるものばかりではないので、お祭り好きの人でもそれは行きづらい、という人もいる。
でも、本来のお祭りの形というのは農村のお祭りが原型です。
まちこは見たい。
でも、こうした身内感覚のお祭りは、どうしても外部の人間が入りにくい状況を作り上げているのも事実。
現に、よその人間が内々の小さな祭礼を見学に行くのはとっても勇気がいることだと思います。
「あそこで見たこともない人が写真撮ってる!」
「ビデオを回している変な人がウロウロしている!」
なんて、現代なら通報もんです。
まちこも、写真撮らないでただしずか~に遠目で見るしかできない雰囲気のお祭りもたくさんあります。
とくに若かりし頃は、区長さんや村の人に話しかけるとか出来んかった。
こうしたお祭りを観たいと思う人は少なからずいます。
そうした人の窓口になってくれるのは、やっぱりお役所の人たち。
少しでも窓口を広げることも文化財維持の一つの努力。
なにも研究をしている人ばかりではありません。
まちこのように趣味でお祭りを観る人なんてごまんといます。
秘儀中の秘儀で、地区の人に口頭に伝える。
外部の人間が入るとこの地区の祭礼の意味がなくなってしまう。
よそ者を入れたくない。(←南房総は結構コレ意識が強い)
そういったどうしようもない事情も多々あります。
そうなると、お祭りは自分たちで維持して行くしかいない。
悲しいかな、これしかないのが現実。
でも、それにも限界があります。
お役所の人が地域の伝統を守るという名目で記録するしかないお祭りもたくさんあります。
その折り合いをどこでつけて、どう維持して行くのか。
役所の中で優先順位が低いなら外部委託するとか。
その地区の区長さんにお願いして、なにか記録をとっておいてもらうとか。
あとになって悔やんでも遅いんだよな~・・・
多分、全国津々浦々、きっと大きなお祭り以外消滅してしまう時代が来ると実感。
嗚呼。
いつも思うのですが、まちこをお役所に売り込み営業でもいくかなぁ(笑)
というわけで、お祭りに興味のある同志の皆さん。
自分の出来る範囲で頑張って参りましょう!
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)