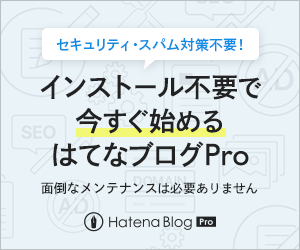こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は昔から千葉県館山市の内陸部にある「豊房(とよふさ)」のお祭りをピックアップしました。
ではでは早速!
豊房祭礼について
豊房地域は、イチゴ狩りセンターや山間にありながら農業が盛んな地区。
農業が色濃い地域なので、秋のお米の収穫に感謝した秋祭りが行われます。
祭礼日
10月の中旬頃に各神社にて開催中。
各神社にて執り行われるので、大きな人の流れを見ることは出来ませんが、
県道188号沿いに、そここで屋台や神輿がいることに気付きます。
祭礼内容
各地区で引き回し等が行われ、夕方JA安房豊房支店の駐車場にそろい年番渡しが執り行われます。
氏子宅で接待を受けたり、各家と密接に結び付いた豊房のお祭りでは「神楽櫃(かぐらひつ)」と呼ばれる特徴ある神輿?のようなものが出祭。
参加地区
大戸、古茂口、出野尾、南条の4地区です。
同日に飯沼、岡田、作名、山荻、合戸も祭礼を行っていますが、合同で集まるものではない様です。
昔は氏子家を周り、軒先まで神輿を進めていたそうで神輿の担ぎ棒は大変短かった!
神輿を屋台に乗せる
大戸(白幡神社)
大戸は館山市街を抜け白浜に向かう道の入口にあたる地域です。
屋台を1台有し、白幡神社を祀ります。
屋台には神輿が乗っており、大きな神楽櫃の印象を受けます。
古茂口(日枝神社)
古茂口は豊房の山間を抜けて南房総に隣接する地区です。
日枝神社を祀っています。
神楽櫃として屋台に神輿を乗せて曳き廻します。
昭和63年に地元の安西工務店が製作したもので、神輿は上須賀から譲り受けたものです。
子供用に、子供神輿もあるそうです。
また古茂口の祭礼の際に行われる獅子舞は、「古茂口獅子舞神楽」として館山市の無形民俗文化財にされており地区の保存会の方々がその伝承を引き継いでいます。
「古茂口獅子舞神楽」については館山市役所ホームページをご覧ください。
※市発行の冊子のPDFで少し画像が荒れていて読みにくいです。
 上須賀ってどこ?
上須賀ってどこ?
出野尾(十二社神社)
館山バイパスを白浜方面に抜ける道にある館山運動公園あたりの地区を指します。
祭神は天御中主尊をはじめ12柱の合祀神社。
鎮守は十二社神社で、白木造りの神輿があります。
初代後藤義光による彫刻で、昭和29年に藤原地区に売却した先代神輿の彫物の一部を残して作られました。
昭和49年に修理がされています。
大戸地区の合同祭にも唯一の神輿として出祭します。
南条(八幡神社)
南条は、館山方面から豊房地区の入る入り口に位置する地区です。
八幡神社が鎮座し、祭礼では屋台を出祭します。
神楽櫃として神輿を乗せた屋台は、地元大工の手によって昭和63年に製作されたそうです。
祭礼時には子供神輿も担がれ賑わいを見せます。
飯沼(熊野神社)
飯沼は館山のバイパスを白浜に抜ける手前にある山間に向かって伸びる道沿いの地区です。
熊野神社を祀ります。
以前は10月17日が祭礼日でしたが、最近10月17日か10月の第2土曜に変更となりました。
豊房祭礼と同日となります。
祭礼日に行われる神事や神輿等の情報は不明です。
岡田(八幡神社)
岡田は館山の白浜に抜ける道すがらの山間の地区です。
鎮座するのは八幡神社で、10月17日か10月の第2土曜日に祭礼が行われます。
以前は10月17日が祭礼日だったそうです。
神事や所有する神輿等の情報はありません。
作名(諏訪神社)
作名は白浜へ抜ける道沿い、長田のすぐ近くの地区になります。
諏訪神社を祀り、祭礼日には子供神輿が出祭すると聞いています。
豊房祭礼と同じ日で、10月17日か10月の第2土曜日に祭礼が行われます
合戸(白幡神社)
合戸は、豊房地区で白浜に抜ける館山と南房総市白浜の間の山間にあります。
10月第2土曜が祭礼日で、平成13年までは10月17日に行われていました。
白幡神社を祀り、人形屋台があるそうです。
後藤実義房作の彫刻で飾られた大正期に作られた2台目です。
1台目は昭和8年に製作され、昭和29年に長須賀に譲ったと言われています。
神楽櫃として神輿を乗せているそうですが詳細については不明です。
山荻(山荻神社)
山荻(やもうぎ)は、 館山を過ぎ南房総市に入る手前の山間の地区です。
白木造りの美しい神輿を有し、子供神輿と併せて出祭します。
台輪に獅子の飾りが施されているのが特徴です。
館山の無形民俗文化財にしていされている「山荻神社筒粥神事(やまおぎじんじゃのつつがゆしんじ)」が、毎年2月26日に行われ農作の吉凶が占われます。
この例祭日以外にも安房国司祭(やわたんまち)にも渡御し、祭りを盛り上げます。
 やわたんまちを見てみよう!
やわたんまちを見てみよう!
< 参考文献・サイト >
- 南房総 花海街道
- 各地区の皆様!!!
- 館山市役所のホームページ
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
神楽櫃は神輿よりもっと近くに神様を感じる~まとめ~

豊房の祭礼の特徴は、神輿のような「神楽櫃(かぐらひつ)」というものを屋台に乗せているところです。
「櫃」とは「箱」の事で、いわゆる入れ物のことをさします。
また「神楽」は単純に歌舞の事をいうのではなく、ここでは「神座(かみざ)」が転じたものととらえるのが近いかな。
神座は”神の宿る所”ですが、そこで降りた神と人が交流のために宴を催した場所とされ、そこで行われた歌舞が「神楽」と言われるようになりました。
もとは神の降り立つところというのが「神楽」の語源。
つまり、この「神楽櫃」とは神様の入れ物といったイメージをしてもらえればいいのかなと思います。
全国各地にあり、神社をギュッと小さくして台車の上にのせたものなど、様々な形状のものがあります。
大きさは大振りのものから、子供だけで扱えるような小さなものまで多種多様。
神輿も神を乗せて練り歩くものなので、「神楽櫃」と同じ。
山車や屋台のように神様を乗せず地区内を曳き回すのは、穢れを払うのが目的なので神輿などとは少し意味合いが違ってきます。
こうした「神楽櫃」のような形のものは安房地域にも多数存在し、比較的内陸の農村部に多いという特徴があります。
また、秋に行わるお祭りで多いことなどから、豊作を神様と共に感謝をする意味合いがあるからではないかと。
まちこ個人的には、氏子と神社の結びつきが強いため、近くにもっと神様を感じられるように箱形にしたのではないかと考えています。
まさか神輿を家の中にまであげるなんて出来ませんが、箱であればお家の中に招き入れることが出来ますから。
豊房のあたりは山間で、山裾を縫うように県道188号線があります。
ここで飲食店や旅館などを探すのは無理なので、比較的ドライブでスルーされてしまうところかと思います。
でも、特徴ある神楽櫃を見れればとってもラッキー。
獅子舞もいるので、あわよくば噛んでもらいましょう。
しあわせになれること請け合い。
また、この地域にある「小網寺(こあみじ)」の梵鐘は国の重要文化財に指定されています。
製作年は弘安9年(1286)の鎌倉時代。
本堂は明治時代に建てられたものですが、その向拝にある彫刻は南房総を代表する宮彫師:後藤義光の作品で、竜の彫刻はすばらしいです。
館山の山間で、ドライブする人にとっては一過程の道すがらでしかありません。
でも、せっかくこちらに来るのなら、こうした地域のお祭りをみるのも、また一つの観光!
だから、ここをドライブスルーしないでね~
豊房の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)