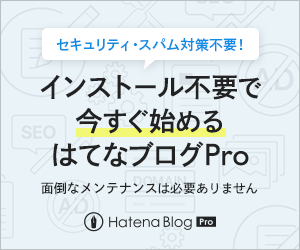こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は昔から千葉県館山市の港町として栄えた「船形(ふなかた)」のお祭りをピックアップ!
船形について
船形は館山市の北西部に位置する港町です。
昔から漁港として栄え、住民は漁業を中心に生活をしていました。
あの新札の肖像画となる「渋沢栄一(しぶさわえいいち)」が建てた学園などもあり、彼となじみのある地域でもあります。
かつては映画館やボーリング場などもあり大変栄えていましたが、今は言わずもがな少子高齢化が進んでいます。
でも、お祭り熱は俄然熱い!
船形祭礼について

館山市船形には、諏訪神社という船形の総社があります。
「船形祭礼」は、この諏訪神社を中心とした船形地区の合同祭。
祭礼日
7月下旬の土日(※本来は7/26、27)です。
※周辺の祭礼の実施状況等によって前後する場合あり。
参加地区
は、船形地区の堂ノ下、濱三(西・東・仲宿)、柳塚、大塚、根岸、川名(川名濱・川名岡)の6区。
祭礼内容
大小併せて14の神社があり、船形祭礼のほかに各神社で4~6月にかけて例祭(「夜店(よみせ)」と呼ばれる)が行われています。
昔は船形村と隣の川名村と別々に行っていたお祭りを明治12年の合併にあわせて、合同で行うようになりました。
全山車・屋台が川名の山車を迎え川名の浜へ行き、今度は川名の山車とともに堂ノ下の浜へ。
その後堂の下の浜で「御浜出」をした後、各山車はそれぞれの地区へ帰って行くのが大まかな順路です。(※「御浜出」は残念ながら現在は御浜出は行われていません)
二日目の夜には、船形の港の道路が歩行者天国となり各地区が囃子を打ち鳴らし競い合う様子は見どころの一つ。
神輿は出祭しませんが、山車や屋台に施された彫刻や立派な幕などは素晴らしいものばかりです。
南房総一の大きさや立派な山車や御船がある
堂之下(諏訪神社)

川名の浜での堂ノ下車
堂之下は船形地区の総社諏訪神社を祀る地区。
破風山車を所有。
現在の山車は明治30年頃に制作されたもの。
乗っている人形は「仁徳天皇」。
※通常は山車の中に格納されていて、必要に際して上下させ人形を出し入れします。
山車は三層になっていて、それぞれがきらびやかな幕に覆われています。
正面上部が破風型になっていることや、山車のブレーキが山車内下部にあるのが特徴の山車。
彫刻は、「加藤清正の虎退治」「獅子と鞠」をメインに後藤喜三郎橘義信によるもの。
 堂之下の山車の詳細はこちら
堂之下の山車の詳細はこちら
濱三(山ノ神・日枝神社・金毘羅神社・稲荷神社)

川名の浜での濱三御船「明神丸」
濱三は、西・東・仲宿の3区合同の名称で、それぞれ山ノ神・日枝神社・金毘羅神社・稲荷神社を祀ります。
房総では度々みられる船型の山車で、「御船(おふね)」と呼ばれ「明神丸」という名前がついています。
船型の山車のため人形はなし。
現在の御船は3台目。
先代は大正12年に関東大震災で焼失し、その後昭和7年に石井一良が製作され現在に至ります。
焼失前は屋根が無かったそうですが、昭和7年再建の際に付けられました。
彫刻は10年間かけて完成。
鳳凰は後藤義政、屋根下の下り龍は後藤喜三郎義信が彫刻。
他にも後藤実義房、後藤滝治義光などが彫刻に関わったと伝わります。
 濱三「明神丸」の御船の詳細はこちら
濱三「明神丸」の御船の詳細はこちら
柳塚(八雲神社・厳島神社)

川名の浜での柳塚屋台
柳塚は船形の中でも広い地区で、八雲神社・厳島神社を祀ります。
山車は人形屋台で、中に納める人形は毎年借りておりその内容も毎年違います。
現在のものは昭和10年に製作され、彫刻部分は以前の屋台のものを再利用。
東京の彫刻師:小島松連の作で、昇り龍下り龍は迫力満点。
 柳塚の屋台の詳細はこちら
柳塚の屋台の詳細はこちら
大塚(神明神社)

川名の浜での大塚山車
大塚は船形の漁港に最も近い地区で、神明神社を祀ります。
大変立派な山車を有し、他地域と比べても引けを取らずまた大き目の山車であるのが特徴です。
南房総で一番大きな山車とも。
現在の山車は明治20年に神奈川県の浦賀から購入したもので、骨組み自体は江戸時代末期のもの。
彫刻師:後藤利兵衛橘義光を中心に明治23年に彫刻が完成。
5~6年もの歳月を費やし彫られた彫刻で大変手が込んでいます。
平成2年に大規模な改修が行われ、美しく生まれ変わりました。
人形は「神武天皇」で、三層のからくりの中に普段は格納され必要に応じて上下。
 大塚の山車の詳細はこちら
大塚の山車の詳細はこちら
根岸(加麻土神社・大六天・御霊様)

川名の浜での根岸屋台
根岸は海から山裾に至るまで長い範囲の地区で、加麻土神社・大六天・御霊様の三社を祀ります。
大正8年に地元大工:青木友次郎が製作した人形屋台を所有。
以前は山車。
正面・背後にある龍の彫刻は圧巻で、彫刻師後藤滝治義光・後藤喜三郎橘義信の作といわれています。
 根岸の屋台の詳細はこちら
根岸の屋台の詳細はこちら
川名(金毘羅神社・日枝神社)

川名の浜での川濱山車
川名は川名濱・川名岡の2地区からなっています。
以前は船形村ではなく独立した川名村でしたが、明治12年船形村と合併。
ここから合同祭がはじまりました。
濱と岡で、それぞれ金毘羅神社・日枝神社を祀ります。
山車を有し、三層の山車の中に臨月の神功皇后を乗せています。
現在の山車は昭和に製作され、昭和11年に彫刻師後藤義孝によって彫刻が完成したといわれています。
 川名の山車の詳細はこちら
川名の山車の詳細はこちら
御浜出(おはまで)

船形の祭礼行事の一つ。
船形の浜に各山車・屋台を毎年年番毎に下ろして、砂浜でそれを曳くというもの。
以前は車輪を外して担いでいたが事故が多かったため、もっぱら曳くようになったと言われています。
そりゃ山車を担ぐって・・・
なかなか引き上げることが出来ず夜中までかかったり、山車を浜に置きっ放しということもしばしばあったらしいです。
船形の漁港あたりから、堂の下の浜までの長い距離を曳いていましたが、人手や浜周辺の設備環境の変化により、距離は徐々に短くなっていきました。
残念な事に現在は行われていません。
その代わりに、諏訪神社下の海岸に向かう坂を利用して山車・屋台を曳き上げる事があります(毎年ではない)。
「おはまで」というと神輿が海につかって身を清める事が良く知られていますが、山車を砂浜におろしてひっぱるこの行事は船形特有のもの。
しおごり
船形祭礼に際して初日に、毎年諏訪神社と金毘羅神社それぞれで行われる祭祀。
若い衆が濡れた新しい砂(「波の華」)を両手ですくい、神社の階段を一気に駆け上がり神前に供えるというものです。
木遣を歌いながら気勢を上げるのが特徴。
しおごりの木遣
ソリャー こぼれ松葉もあれみやさんせ、枯れて散るとも二人づれ。
山車引きの木遣
ソリャエ そでも身ごろも良く聞き給え、母がたびたび苦労する。
ソリャエ 船のみよしに鶯とめて、明日は大漁と鳴かせたや。
ソリャエ 岩にたたかれ荒瀬にもまれ、苦労尽くして上るこい。
ソリャエ 富士の白雪や朝日にとける、娘島田は寝てとける。
ソリャエ 色でも西瓜でさえも、中にゃ苦労の種がある。船形史考 石渡進 他(船形小学校PTA)昭和55年より
その他参加する祭礼
各地区とも船形祭礼の他に、南総里見祭りに参加することも。
南総里見祭りはその年により参加・不参加があるので、詳細については一般社団法人館山市観光協会の案内を参考にしてください。
< 参考文献・サイト >
- 船形史考 石渡進 他(船形小学校PTA)昭和55年
- 南房総 花海街道
- 各地区の皆様!!!
- 館山市役所のホームページ
大漁旗は昔から~まとめ~
昔から大漁旗を振るのがこのお祭りの特徴で、漁師町のお祭りというイメージがすっかり地元では定着している感じ。
こうした地区全体のお祭り以外に、各神社で例祭を行っているのでお祭り好きの人たちというのも良く知られています。
今ではすっかり静かな漁村になりつつあります。
泊まるところや食事処を探すのはちょっと大変かもしれません。
電車の本数も激減していますので、こちらに来るときには大体みんな車で来てる方が多いです。
※ちなみに、船形のJRの駅「那古船形駅」はAKBの「会いたかった」PV撮影場所でも有名。
インター下なので他県からの車が多いのですが、ぶっちゃけよその人びっくりします。
え?
だってこんな片田舎にあんな立派な山車があるなんで誰も思わないみたいだから、みんな車の中からバシャバシャ写真撮ってます。
うれしい反面、ここにとどまれ~と念をかけるまちこでした。
船形の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)