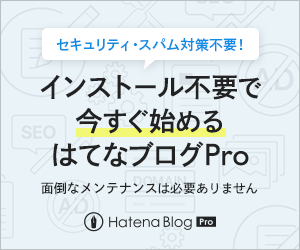こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は、古来から実り豊かな地で現在も米どころ、千葉県南房総市「三芳(みよし)」の秋の豊作祭をピックアップ。
ではでは早速!
三芳の秋祭りについて
温暖な房総半島にありながら内陸にあるため、涼しく冬には雪がよく降る三芳。
この寒暖差を利用して、農業がとっても盛ん。
特にみかんなどの山間を利用するものや、酪農なども多く、種類は多種多様。
三芳にある道の駅鄙の里には、三芳でとれた牛乳を利用したデザートを食べることが出来ます。
アイスそんなに好きではありませんが、唯一1個全部食べられる一品。
そんな三芳は、縄文時代からの遺跡にはじまり、戦国時代里見氏の城跡などもあり、歴史が古い地区でもあります。
滝田城跡は南総里見八犬伝の最初の舞台で、実際の史跡としても八犬伝の観光スポットとしても知られています。
また、下滝田にある戦中の遺構であるロケット特攻機「桜花」の発射台も有名。
今はのどかな田園風景ですが、こんな身近に戦争の名残があるのかと思うとちょっとドキッとしますよね。
ちなみにここから「桜花」は一度も発射されなかったそうな。
ここで開催されう三芳の秋祭りは、旧三芳村の市街地を抜け山間の地区で行われる祭礼。
祭礼日
毎年10月の第2土日に行われますが、その周辺区域も「十日祭(とおかまち)」といい秋のお祭りシーズン。
どこに行ってもお祭りお祭りで、きっとびっくりします。
祭礼内容
昔は千代にある皇神社を総社として明治頃まで祭礼をしていたそうですが、現在はこれを引き継いだ形の行事は残っていません。
各神社とも例祭日は夏。
合同祭として秋祭りを10月の十日祭として一同に開催しています。
三芳の祭礼は地区の都合により祭礼日が違ったり祭礼を行わなかったりします。
でも、三芳に限らず南房総では、10月の第2土日はどこかでお祭りが行われています。
ハズレなし。
参加地区
池之内、上滝田、大畑、下滝田、千代、中(中村)、山名の7地区。
担ぎ屋台の魅力
池之内(熊野神社)
池之内(熊野神社)池之内は安房グリーンラインと千葉県道296号との交差点を囲むようにある地区です。
鎮守の熊野神社も交差点近くにあります。
明治までは神輿で参加していたそうですが、三芳の秋祭りでは屋台が出祭します。
現在のものは2台目で、昭和21年に地元の大工が製作しました。
後藤喜三郎橘義信の彫刻が彫られ、平成15年に屋根の改修が行われました。
以前の屋根は三芳の中村に譲ったそうです。
これと併せて、昭和25年に新たに神輿が作られ(地元大工作)出祭しています。
上滝田(白山神社)
上滝田は、滝田郵便局周辺の地です。
鎮守は白山神社。
創立は元応2年(1320)で、境内には武田石翁の手水石があります。
担ぎ屋台を所有しています。
後藤滝治義光による彫刻が見られます。
神輿は昭和3年制作され、重さ500kgと言われています。
白木造りの神輿でしたが、現在は担ぎ手不足の為出御はしていないようです。
ただし2011年の「まほろば祭り」に出祭しています。
大畑(?神社)
大畑は上滝田の一部で、上滝田東側の地区になります。
小祭用担ぎ屋台があるそうですが、現在は休止中です。
上滝田の一部なので、鎮守は白山神社でしょうか?
下滝田(滝田神社)
下滝田は三芳の道の駅鄙の里から奥、の千葉県道88号線沿いの地区です。
滝田神社を祀ります。
もとは諏訪神社として寛永2年(1625)創立しましたが、明治41年八雲神社など他2社を合祀し現在の名前になりました。
後藤滝治義光による彫刻が彫られた担ぎ屋台を所有します。
また、明治初期に購入した神輿があります。
滝田神社に合祀した神社の内、八雲神社の神輿だったそうです。
神輿出祭の滝田神社の例祭日は7月9日(7月第2土曜)です。
千代(皇神社)
千代は三芳の道の駅鄙の里の裏手の地区になります。
鎮守は皇神社です。
明治以前は担ぎ屋台でしたが、その後明治初期に曳き屋台に改造し現在に至ります。
昭和59年頃に製作(彫刻は再利用)、昭和63年に館山のどこの地区か不明ですが、当初の屋台を小さくしたものを譲ったそうです。
明治初頭まで総社として、毎年8月に近隣の神社から獅子舞や神楽などがやって来ていたそうです。
明治維新後から中期まで4村(どこかは不明)の神輿渡御、その後上堀・三坂の神輿渡御、上滝田・下滝田・千代の屋台がやって来ていたそうですが、いずれも現在は行われていません。
中(中村)(駒形神社)
中は安房グリーンラインと千葉県道296号との交差点を更に進んだところ、池之内の先にあります。駒形神社を祀ります。
昭和22年に人形屋台を製作し、昭和50年代に改修が行われ今に至ります。
山名(八雲神社)
山名は旧三芳村と旧丸山町の境にあり、三芳の祭礼での地区では最も東の地区になります。
八雲神社が鎮座します。
明治27年に地元の宮大工により製作された神輿があり、こちらは子供神輿として出祭します。
大人神輿は明治39年頃に奉納。
昭和35年頃に両方ともに塗替えが行われています。
八雲神社の例祭日は7月15日です。
< 参考文献・サイト >
- 各地区の皆様!!!
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
三芳は古来から実り豊かな地

三芳は昔から農業が盛ん。
それは今でも変わりません。
土地がとっても肥えているため、農作物はもちろん猿や鹿など動物たちのすみかでもありました。
上滝田を千葉県道258号線を更に進むと、増間(ますま)という地区があります。
この増間にある大日堂という山には増間の鎮守日枝神社(宝暦6年(1756))が祀られています。
ここで毎年3月1日に歩射神事(弓で的を射って豊作などの吉凶を占う)が執り行われます。
千葉県の無形民俗文化財にもしていされている貴重な神事で、由来記によると正元元年(1259)とも。
実はこの神事、日枝神社すぐ後ろの鹿島山に残されている伝承からはじまり。
伝承は以下の通り。
奈良時代の初めに大飢饉にあった増間。
鹿島大明神から弓を授かり鳥獣を獲り飢えをしのぐよういわれます。
もともと鳥獣の多い土地柄、増間の人々はこれで救われました。
鹿嶋明神に感謝をし、これを鹿島山に祀ったそうな。
鹿島明神は現在の日枝神社のすぐ後ろに石碑を建てて祀られています。
日枝神社も御祭神も大山咋神(おおやまくいのかみ)は五穀豊穣の神でもあることから、鹿島山の伝承と日枝神社の神威が相まって今の形になったようです。
南房総にはこうした鳥獣を狩るという伝承が各地で残されています。
例えば、安房の開拓時代にも鹿が邪魔して大変だったよ。
ってことで、下立松原神社のミカリ神事がはじまります。
 白浜の滝口神社にも害獣駆除の歴史あり
白浜の滝口神社にも害獣駆除の歴史あり
三芳に限らず南房総では、昔から鳥獣に悩まされるぐらいその数が多かったようで。
イコールそれだけ自然豊かな地であったともいえます。
今でも南房総はイノシシやサルが多くて困ってます。
猟友会の皆さんが頑張っていますが、若手はめっきり。
そこで千葉県では若手のハンターを育成するために猟銃取得相談も行っています。
試験内容は別にしても、保管や維持に関して猟銃はとても厳しいし&高価です。
警察も介入しますしね。
あとは罠の設置にも免許が必要ですから、なんだかんだめんどくさいです。
ちなみにまちこも猟銃試験の免許は合格してます。
が、だいぶ前なのでもう失効してるかな。
↓ 参考までにこんな問題集やりました。
でも、若手の皆さん!
猟師目指すってのも一つの職業選択だと思います。
就職するってのもいろんな道があるもんです。
ところで、イノシシって食べた事ありますか?
いわゆるジビエって料理ですが、おいしいイノシシはめっちゃおいしいです。
鹿は寄生虫がいるから気をつけろと親父様に教わりました。
サルは臭くてくうもんじゃねぇとも。
一番はキジですかね。
ウサギはめっちゃ硬い。
ジビエ料理を提供してくれるお店も最近は増えましたので、ご興味がある方は食すべしです。
そう考えると、昔から三芳は食べるものに困らないところだったようです。
だから海側の魚とか食べたことないって?
いやいや、そこは農作物との交換等々交流が多かったようで、三芳の人たちは大変潤っていたそうです。
だから、やさしい人たちが多いです。(まちこの独断と偏見です)
三芳のお米や農作物が食べたかったら、道の駅「鄙の里」へ。
あと、三芳の名物は「グリーンピースごはん」。
まちこは苦手だ~~~~・・・・
おいしいもの食べながら三芳の秋祭りにも来てくださいね~
三芳の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)