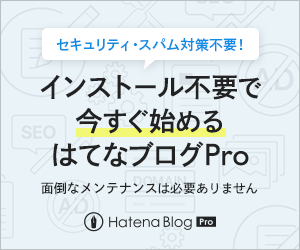こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
館山市では、「やわたんまち」「館山地区合同祭」などが有名ですが、各神社で個々にお祭りをやっているところがたくさんあります。
今回は、館山市に点在する祭礼を集めてみました。
ではでは早速!
館山市に点在する多数の祭礼
曳船祭り(相浜・相浜神社)
例祭日
3月最終土曜
鎮守
相浜神社(大正時代に相浜地区二斗田と松崎の合祀となる)

相浜神社の「波除丸」(写真は安房神社例大祭1300年記念祭にて)
館山市街地を西岬地区方面海沿いに抜けた海岸沿いにある地区。
かつて安房神社例大祭に神輿が出祭し浜降「磯出」神事の先導役を努めていましたが、現在こちらの例大祭には出祭はしていません。
相浜神社例祭である「曳船祭り」には神輿が出御。
曳船祭りは、相浜の名主石井家を殿様が訪れた際舟遊びを見せたことが始まりとされます。
祭りでは、殿様役の子供が地区の若衆に担がれ、その通り道には浜から運んだ砂で敷き詰められていたそうです。
この際に練り歩いた御船「波除丸」は、現在曳き手がおらず残念ながら町内の曳き回しは行われていません。
この波除丸は、他の地区の御船と比べて水押(船の先端のとがっている所)の角度が緩く、朱塗りの雅な姿をしているのが特徴。
後部は明治34年に後藤喜三郎橘義信によって彫られたとされます。
明治30年頃、昭和33年、昭和54年に改修。
曳船祭りの情報は館山市役所ホームページで見れます。

相浜神社正面の様子
 波除丸の写真をもっと見たい方はこちらの記事へ
波除丸の写真をもっと見たい方はこちらの記事へ
波佐間祭礼(波佐間・諏訪神社)
例祭日
7月1日
鎮守
諏訪神社
備考
南房総地方のミノコオドリ(国記録選択文化財)
祭礼内容
西岬地区にあり、南房総市千倉町川口の鹿嶋神社とともに例祭時に踊られる「ミノコオドリ」は国の文化財に指定されています。
相模湾西岸(神奈川県小田原市から静岡県東伊豆町)にある「鹿嶋踊」と共通点がありますが、少女のみで行われる人数に制限がないなど南房総独自の民俗芸能でもあります。
ミノコオドリについては(国指定)南房総地方のミノコオドリ | 館山市役所をご覧ください。
例祭時には神輿1基、子供神輿1基が出御。
神輿の詳細についてはわかりません。
川崎祭礼(川崎・八雲神社)
例祭日
7月第1または第2日曜
鎮守
八雲神社
祭礼内容
本来は那古地区に属する地区ですが、正木に入ります。
どちらの地区にも関係しているものの、例祭は八雲神社単独。
本祭は正木地区の諏訪神社で、昔より神輿を渡御させています。
川崎地区には昭和7年に作られた白木造りの神輿と明治25年製作の人形屋台あり。
後藤喜三郎橘義信彫刻の「赤穂浪士」の彫刻が施された人形屋台は安房地区で最も大きい屋台と言われています。
平成23年に大改修。
神輿は以前は白木造りで昭和の初めごろにつくられたもの。
「御浜出」もありますが、今まで神輿が海に入ったという話はないそうです。
祭礼では、海に近い祭礼ならではの「潮垢離(しおごり)」神事が行われます。
祭り前日の夕方に子供たちが、川崎の浜で砂団子を作り拝殿にお供えするといものです。
しおごりというと、海で身を清めることと認識されていますが、南房総では自治区の海浜の砂を神社に奉納するという形が多く見られます。
 正木祭礼にも参加
正木祭礼にも参加
伊戸祭礼(伊戸・八坂神社)
例祭日
7月13日
鎮守
八坂神社
祭礼内容
西岬地区の平砂浦のあたりで、漁港もありダイビングも出来る海沿いの地区の中でも海に大変恵まれている地区でもあります。
神社の由来等については不明です。
古い様式を残す神輿がありますが、現在は担ぎ手不足の為拝殿内に安置のみ。
少し前まで「お浜出」などの神事も行われていたそうですが、残念です。
布良祭礼(布良・布良崎神社)

布良崎神社の神輿(写真は安房神社の1300年例大祭にて)
例祭日
7月第3土曜・日曜
鎮守
布良崎神社
祭礼内容
西岬地区で、海を臨む海岸沿いの高台に布良崎神社を祀ります。
かつては安房神社例大祭にも出祭していましたが、現在は参加していません。
所有する神輿は「大天皇」と呼ばれる房総一の重たいものと言われ、時代を遡るほどその重さは大きかったとされています。
後藤喜三郎橘義信による彫刻が施され、昭和57年、平成21年に修複が行われています。
昭和天皇の即位式に東京を中心とした周辺地域から1000余りの神輿が皇居前広場に集まったことがあるそうですが、この祭典に布良崎神社の神輿も参加したという話が伝わっています。
神余祭礼(神余・日吉神社)

日吉神社の神輿(写真は安房神社の1300年例大祭にて)
例祭日
7月19、20日
鎮守
日吉神社
祭礼内容
館山と白浜を結ぶ県道沿いの地区で、平安時代からの歴史を持ち神余氏の拠点でもあったため山間にありながら、広い敷地と立派な神殿を持つ日吉神社に守られています。
この日吉神社例祭で行われる鞨鼓舞(鞨鼓(かっこ)とは太鼓の事)は200年前より続く伝統芸能として館山市無形民俗文化財に指定。
併せて行われる巫女舞とともに五穀豊穣、一家繁栄などを祈ります。
例祭で担がれる神輿は大変重く、昭和26年に作製、彫刻は三代後藤義光、もとは白木造りでした。
平成6年に塗り替えられ、色彩豊かな美しい神輿へ。
長須賀祭礼(長須賀・熊野神社)

長須賀の屋台(写真は里見祭りのもの)
例祭日
7月第3日曜を含む土日
鎮守
熊野神社
祭礼内容
館山市街の商店街を担う地区です。
昔より宿場町として栄え、県無形文化財の唐桟織や伝統工芸が有名。
1日目に神輿、2日目に屋台の引き回しが行われます。
神輿は明治26年に作られたもので、後藤利兵衛橘義光の彫刻。
「小殿」と呼ばれる一回り小さい神輿も同時期に作られました。
また、昭和30年に作られた屋台は、館山市内でも1,2の大きさを誇ります。
特徴はせり出した踊り舞台で、正面破風に飾られた鳳凰(彫刻師後藤義孝作)も目を引く屋台。
平成17年に改修が行われ、今も当時の部材が大事に使われ、内幕も唐桟織であることなどから大変見どころの多い屋台です。
明治29年に豊房地区大戸から屋台を譲り受けているという情報がありますが、詳細は不明。
神輿は、初代後藤利兵衛義光の彫刻で飾られています。
市内でも初代義光の作品は少なく、貴重な作品。
例祭の他に南総里見祭りに出祭することがあります。
南総里見祭りの詳細については南総里見まつり公式ホームページにて確認下さい。
 長須賀の屋台の写真をもっと見たいなら
長須賀の屋台の写真をもっと見たいなら
洲崎神社例祭 (洲崎・洲崎神社)
例祭日
8月20~22日
鎮守
洲崎神社

洲崎神社正面鳥居
祭礼内容
館山市の南、海沿いの高台に鎮座する洲崎神社は、安房神社の后宮である「天比理乃咩命(あまのひりのめのみこと)」を祀っています。
同じ天比理乃咩命を祀っている洲宮神社とは長い間その社格等についての論争があります。
一説には洲崎神社を拝殿、洲宮神社を奥宮とし、一つの神社であったともされていますが、詳しい事はわかっていません。
海上の守り神であることから東京湾一帯にその信仰があり、今ではこの近くに分社された海底神社なども良く知られているところです。
8月の例祭時と2月に行われる「ミノコオドリ」は、千葉県無形民俗文化財になっています。
鹿島信仰(悪霊払い)・弥勒信仰(富や豊作)の流れを組み、昔は男性が行っていたが現在は女児が行います。
同じ系統のもので、波佐間のミノコオドリは国の文化財に指定。
神輿を一社で3基所有しており、全て例祭に出祭。
大神輿・中神輿・子供神輿の3基で、白木造りで統一感のある3基です。
祭りでは、神輿と猿田彦に扮した者とともに洲崎神社の長い階段をおり目の前の浜に行く、御浜出神事が行われます。
3日間行われる祭礼は、ミノコオドリ、神輿渡御、地元の芸能祭が行われ、地域ぐるみの昔からのお祭りの流れを守っています。
※同じく西岬地区の西川名(厳島神社:館山市無形民俗文化財「湯立神事」)の屋台1台と、坂田(熊野神社)の神輿1基も洲崎神社例祭と同日に祭礼がありますが、合同で行われているのか単独なのか、祭りの詳細や所有している神輿等は不明です。
 洲崎神社のあれこれ
洲崎神社のあれこれ
安布里祭礼(安布里・八坂山神社)
例祭日
7月半ば
鎮守
八坂山神社
祭礼内容
館山のいちご狩センターなどがある館山駅から東へ行った開けた地域。
神社の由来等については不明ですが、もと大網地区にあった山神社と八坂神社が明治に入り合祀され、この名になったようです。
神輿は牛頭天王の神紋をかがげた神輿があります。
昔は北条海岸に浜下りにいっていたそうです。
坂田祭礼(坂田・熊野神社)
例祭日
8月第4土曜日
鎮守
熊野神社
祭礼内容
西川名同様洲崎神社のすぐそばの地区。
坂田は「ばんだ」とよみます。
神輿は三尺神輿で、平成6年群馬県高崎にて製作されたもの。
先代の神輿は今より一回り大きかったそうです。
「御浜出」では実際に海に入ります。
安東祭礼(安東・熊野神社)
例祭日
7月最終土曜日
鎮守
熊野神社
祭礼内容
JR九重駅から東に少し進んだところにあります。
神輿は黒塗りの勾配の少ない屋根の神輿。
< 参考文献・サイト >
- 南房総 花海街道
- 各地区の皆様!!!
- 館山市役所のホームページ
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
なんで館山はお祭りが多いの?
なんで館山はお祭りがそんなに多いの?とよく他県の友人から聞かれます。
そりゃお祭りが好きだからだ!
と、いいたいところですが(いや、これもあるのですが)、実際の背景はちょっと違います。
現在、館山市や南房総市などの安房地方は陸の孤島として、少子高齢化がめっちゃ進む過疎地です。
しかし、これは現在のお話。
実は昔はものすごくお金持ちの地域だったんです。
東京から離れることを「下る(くだる)」、東京に行くことを「上る(のぼる)」といい、現代人は普通に使っています。
でも、昔の日本の中心地は京都。
だから、そこを基準にすると、安房地方は現:千葉市や現:東京よりも都に近いという扱いになるんです。
なぜなら、海路が優先されたから。
千葉県は、上から「下総」「上総」「安房」という国に分かれていました。
ここにもその一端が見えます。
一番東京に近いところが「下」になっています。
だから京都の都からは、「安房」⇒「上総」⇒「下総」という順だったわけです。
そして、海に突出していたことから、近現代になるまで海の交通の要所、漁業の港の拠点として、全国から人が出入りしていました。
館山は、古代も今も四国や紀伊の国とのつながりが深く、四国にご先祖様の由来があるというお家もたくさんあるんです。
ちなみにまちこのお家も四国の方らしいです(定かでないけど)。
人がたくさん出入りしていた、ということは、それだけお金も動いていたということにつながります。
漁業や海洋交通関係で、安房地方は大変裕福で、江戸時代にはすでに10万人を超える人口密集地域であったことがわかっています。
そうした様々な地域の人たちの住む安房では、その人たちを結束させるものが必要でした。
それがお祭り。
しかも、豊漁、豊作など、どちらの面でも有効な手段だったため、特に江戸時代以降またたくまにお祭りが各地に広がります。
安房地方の神社の数は、全国的に見てものすごく多いというわけではありません。
でも、神輿や山車の所有率はトップクラスと自負出来ます。
大体、1神社に最低1基。
多い所だと、神輿3基、山車1台とか。
こういうのザラにあります。
そして、ここから安房地方、いわゆる房州人のお祭り好きというものが広がって行ったんですね。
でも、当時のように若い人も多くなく、お金がめぐりめぐって裕福な地域かというとそうでもなくなってきた現在。
維持するのも、開催するのもとっても大変なのです。
いつかなくなることを想定するのは悲しいですが、もしかしたら「今」しか見れない貴重な無形文化財になるかも。
いやいや、なくならないようにせねば。
ブログ頑張ろう。
というわけで、みなさん館山に来たらお祭り見て行ってね~
地元の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)