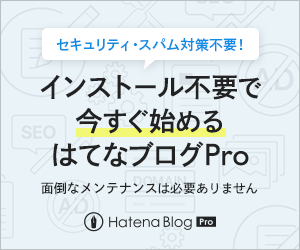こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は、千葉県に現存する数少ない流鏑馬神事が執り行われる吉保八幡神社、千葉県鴨川市「吉尾(よしお)」の祭礼をピックアップ。
ではでは早速!
吉尾祭礼について

吉保八幡神社の境内
鴨川市は南房総の太平洋側にある市で、安房の中でも主要市の一つです。
鴨川市には房総を横断する長狭街道(千葉県道34号線)があります。
この道は、江戸時代から栄えた道で、東京湾と太平洋を一本でつなぐ道として重宝されていました。
※今では鋸南町と鴨川市で長狭街道駅伝競走大会とかやってます。
「吉尾祭礼」が行われる吉尾地区は、この長狭街道ちょうど中間にある開けた土地で、発掘調査などからも古代からの歴史のある土地とわかっているところ。
歴史はとっても古い。
なので、吉保八幡神社をはじめとし、古い神社やお寺が多く残る地でもあります。
この地域で、吉保八幡神社を中心に行われるのが「吉尾祭礼」。
祭礼日
9月の最終土日曜に吉保八幡神社を中心に行われるます。
祭礼内容
神輿8基、屋台5台、宮立と呼ばれる太鼓9基が出祭します。
「宮立て」は、神社をギュッと小さくしたものに太鼓をくっつけた余興物。
小さくても伊八などの彫刻がされていて美術的・歴史的価値があり大変おもしろい出し物です。
日曜日に吉保八幡神社で行われる流鏑馬神事にあわせて、境内に屋台たちが集合します。
参加地区
大幡、北風原、寺門、横尾、細野、松尾寺、大川面、仲、宮山・八丁の10地区。
 鴨川の山間は宮立てがたくさん
鴨川の山間は宮立てがたくさん
宮立という名の小さな芸術
大幡(皇太神社)
吉尾地区は鴨川市海側より内陸に入った長狭海道沿いにある地区で、鴨川市街からみると大山千枚田手前に大幡(おおはた)はあります。
鎮守の皇太(大)神社(こうたいじんじゃ)は、由緒等は不明ですが元禄2年(1689)に本殿が建立されていることが記録に残っています。
吉尾の祭礼には神輿出祭。
白木造りのさっぱりした神輿です。
平成13年に打墨から屋台を譲り受け、先代屋台は廃絶。
先代の屋台は、昭和40年丸村(旧丸山町の丸か?)から譲り受けたものだそうですが、ほとんど使用することはなかったようです。
当初は万灯型の置き屋台を製作し、それを出祭。
 打墨の祭礼
打墨の祭礼
北風原(春日神社)
北風原(ならいはら)は、長狭海道沿いにある吉尾地区の中の真ん中あたりにある地区で、街道を挟んで左右に細長く伸びる地区。
春日神社を鎮守とします。
御祭神は天兒屋根命(あめのこやねのみこと)で、通称明神様といわれています。
文治元年(1185)に農耕地灌漑の守護神として、春日大社から分霊。
昭和8年に永井菊松、鶴岡政吉らによって製作された人形屋台があります。
神輿ーは明治5年以前に作られたもので、昭和に入り何度か改修。
直前の日曜に区内曳き回しが行われているようですが、詳細は不明。
神輿は幅が130センチと大型で、天津小湊町と合併するまで鴨川一の大きさを誇っていました。
昔旧三芳村の滝田から譲り受けたもの。
ちなみに両地区の古老のはなしはぴったり合致するもので、滝田側は「あんまりにも大きくてよそにくれてやった」といい、北風原側は「滝なんとかというところから山越えしてもらってきた」といっています。
「やわたんまち」にも出た由緒ある神輿らしく、「滝」がつく滝口の下立松原神社のものとも推測もされています。
おもしろい由来のある神輿です。
毎年7月の第4日曜日には、北風原の羯鼓舞(千葉県指定無形民俗文化財)が行われます。
以前は北風原の春日神社と横尾の請雨山(しょううさん)の愛宕神社で毎年交代で行われたのですが、今は春日神社で行われます。⇒北風原の羯鼓舞/鴨川市ホームページ
仲(吉保八幡神社(きっぽはちまんじんじゃ))
仲は長狭郵便局から長狭中学校までの長狭海道沿いの地区で、吉尾祭礼の吉保八幡神社を祀ります。
御祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)・天穂日命(あめのほひのみこと)。
天長6年(829)素戔鳴命(すさのおのみこと)・天穂日命を吉尾地区の鎮守神として祀ったのが始まり。
八幡神社になったのは天正15年(1587)で、緒形加賀守茂次が宇佐八幡を勧請し、しばらく廃れていたものを再興したことによります。
明治7年の屋台があり、初代後藤義光の彫刻で飾られます。
昭和33年ごろ火災により獅子木鼻を焼失したそうですが、後藤義孝により補修されました。
吉尾祭礼の日曜日には、鎌倉時代より続く流鏑馬神事が行われます。
その由来は不明ですが、禰宜(神主さん)が騎射することなどから、武芸としてではなく神事としての色がとても濃く古来の形を残しているということで、千葉県指定無形民俗文化財になっています。⇒吉保八幡のやぶさめ/鴨川市ホームページ
また、本殿向拝には初代伊八の作品も残されており歴史を感じられる神社です。
大川面(神明神社)
大川面(おおかわづら)は、長狭中学校交差点から国道410号沿いの地区になります。
神明神社が鎮座します。
古老によると昔「神明の松」という大樹があってその根本に天照大御神が祀られていました。
しかし、その木が枯れてしまったことを機に村内安全を祈願して文明元年(1469)に社を建てたそうです。
※手持ちの資料が仲(八雲神社)とごっちゃになっているため、屋台に関しては下記を参照ください。
仲(八雲神社)
長狭街道をそれて、酪農の里近くの地区。
八雲神社を祀ります。
創立は不詳ですが、口伝によると山神社を八雲神社に合併したことが元永年間(1118~1120)といわれ、歴史は大分古い神社のようです。
人形屋台が出祭し、彫刻師は後藤利兵衛橘義光で明治17年に製作。
平成元年に八丁・水田一夫が改修をしています。
※手持ちの資料が大川面(神明神社)とごっちゃになっているため、この屋台情報が現在中に浮いてしまっています。
旧暦6月15日(7月27日頃)の当地区の八雲神社、牛頭天王祭りに小型の曳き屋台が出祭するそうですが、毎回ではないようです。
寺門(春日神社)
寺門(てらかど)は長狭海道沿いの長狭寺門郵便局周辺の地区になります。
鎮守は春日神社で、御祭神は天兒屋根命(あめのこやねのみこと)。
永禄10年(1567)に里見氏の重臣正木氏の土豪であった粕谷時家によって創建されました。
ちなみに吉尾地区には粕谷姓が多いことでも知られています。
残念な事に屋台は廃絶。
八丁(?神社)
吉尾地区の南の方の地区で、祀られている神社についてはわかりません。
屋台は廃絶。
細野(熊野神社)
細野は鴨川市街から長狭中学交差点を過ぎて、寺門と道を挟んで向かい合う地区。
熊野神社を祀ります。
通称「御熊野様(おくまんさま)」。
創建年は不明ですが、御神体は明和5年(1768)に京都の大仏師福田曽平がここに来た時に作られたものといわれています。
屋台は廃絶していますが、熊野神社に部材の一部を保管。
神輿は吉尾祭礼に出祭しています。
明治か大正初めに作られた神輿。
松尾寺(八幡神社)
松尾寺は細野地区に囲まれるようにある小さな区です。
長福寺の境内に八幡神社を祀ります。
祭神は誉田別命(ほんだわけのみこと)。
創立は不明ですが、慶長9年(1604)正木時茂が建てたと伝わっています。
本殿は慶応年間(1865~1868)に建て直し。
昭和3年に曽呂・畑から担ぎ屋台をもらい曳き屋台に改修し、人形屋台として吉尾の祭礼に出祭しています。
宮山(宮山神社)
宮山は長狭中学交差点から、道の駅みんなみの里に向かって続く地区です。
鎮守の宮山神社は、息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)が御祭神。
創立はよくわっていませんが、慶長年間(1596~1615)に里見氏家臣正木大膳道種が奥さんの懐妊でここを安産祈願所としていたそうです。
そのため「子安大神」と親しまれていましたが、神仏分離令により宮山神社と改名。
吉尾の祭礼では人形屋台が出祭します。
宮山地元の大工・太田五良平藤原政信により、明治期に製作。
横尾(横山神社)
横尾は国道410号よりちょっとはずれた位置にある地区です。
神社は横山神社。
御祭神は大山祇命(おおやまくいのみこと)で昔は横山明神といわれていましたが、神仏分離令により横山神社と改称されました。
創建は元和6年(1620)。
屋台は廃絶され、彫刻の一部が常秀院にあると聞いています。
< 参考文献・サイト >
- 安房の昔話
- 各地区の皆様!!!
- 観光/鴨川市ホームページ
- 吉尾のあゆみ
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
吉保八幡神社の流鏑馬神事が貴重な理由

吉保八幡神社正面
鴨川の漁業は、江戸時代に入って紀州(和歌山)から来た漁師たちが「まかせ網」という漁法を教えたことからはじまります。
それまではむしろ農業が盛んで、主に吉尾地区などの長狭街道沿いの内陸が中心の地でした。
長狭の語源は「長麻(ながあさ)」が転じたもので、当時ここら一帯は良質な麻が採れるところだったからだそうです。
また、「長狭米」といえば南房総に限らずおいしいお米としても知られており、古くから米どころであったことでも有名。
そのため農業を中心とした生活だったので、どうしても稲作などの豊作不作、根付けの時期などが重要でした。
そこで始まったのが吉保八幡神社の流鏑馬神事。

馬場に設置された看板
もともとの由来などは全くわかっていませんが、社伝で鎌倉時代中期まで遡ることが可能。
実際には、もっと古くから形こそ違えどこういった神事が残っていたようです。
そもそも、「流鏑馬(やぶさめ)」とは鎌倉時代に武士の武芸の一つとして確立したもの。
平安時代後期から馬上の弓術としてあったものの、これがイコール神社の神事として出来上がって行ったのは後日談の話。
吉保八幡神社にどんな形でこうした神事が残されていたかはわかりませんが、宇佐八幡宮から勧請(神様の御霊をわけてもらって迎えること)された時期は天長6年といわれ、平安時代初期にあたります。
神社が例祭を行うのは昔から変わりません。
という事は、少なくとも平安時代初期からこうした五穀豊穣や吉凶を占う神事が行われていたことがわかります。
また八幡様というと武士の守り神と扱われてしまいますが、吉保八幡のもともとの御祭神は素戔鳴尊と天穂日命。
素戔鳴尊というと八坂・八雲神社などに祀られる厄除け的な神様と思われがちですが、実は「豊穣の神」でもあります。
天穂日命も農業神であったので、長狭の吉尾地区の「五穀豊穣祈願」がその起源と考えられています。
だから、吉保八幡神社の流鏑馬神事は「武士の神事」ではなく「農業の神事」というわけです。
神主さんが代々引き継いできたというところにも、その断片がみえます。
よくぞ武士に染まらず残してくれました。
と、感謝するべき貴重な神事。
他のところだと、神事的な要素より武芸的な要素が目立ちます。
この要素が、千葉県の文化財に指定されたところ。
貴重な流鏑馬神事や、宮立てという特徴ある出し物もある。
見どころたくさんのお祭りです。
近くには米どころを象徴して、安房の日本酒の代表:寿萬亀(じゅまんがめ)を製造する亀田酒造もあります。
長狭街道を散策しなかがらゆっくり歩くのもおすすめです。
吉尾の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)