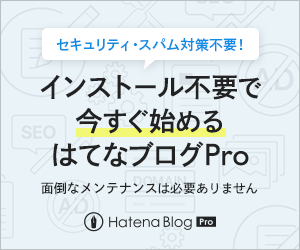こんにちは。
弱小文化財応援ブログ「おらがまち」まちこです。
田舎の祭礼なんて誰も見ないよ?
有名どころでないお祭りは人知れず廃れていく運命ではありません!
地元のお祭りを少しでも全国の皆さんに知ってもらうべく、ブログにて絶賛紹介中です。
片田舎のお祭りだからと南房総の祭礼をあなどるなかれ。
今回は千葉県南房総市「平群(へぐり)」のお祭りをピックアップしました。
一説には、奈良県の平群の人たちが移住してきた土地とも言われる古い歴史を持つ土地。
しかも、この千葉の平群は、南房総のお祭りに多大な貢献をした地区でもあります。
ではでは早速!
平群祭礼について

春日神社にある八房と狸の像
「平群(へぐり)」は、南房総市の山間の地区。
同地区と同名の平久里川沿いに開けた地区です。
ここは南総里見八犬伝の舞台となる犬掛(いぬかけ)古戦場や安房国府(諸説ありどこにあったかは現段階でも明らかでない)などがあったとされています。
南房総のお祭りには特徴的なお囃子が存在します。
通称「平群囃子(へぐりばやし)」といいます。
平群はこの「平群囃子」発祥の地。
さらに平群の中の「米沢」がそれとされていますが、詳細は不明。
今でも引き継がれている平群囃子は、現在、平群の山田地区が「平群囃子保存会」として担っています。
また、各地区で小祭も行われ、それぞれでさらに小屋台を所有しており、最近十数年ぶりに復活させるなど祭礼の維持継承にとても積極的な地域でもあります。
祭礼日
「平群祭礼」は、この山田地区の天神社を中心に行われ、毎年10月第3土に開催。
昭和45年頃に祭りを再開し、昭和50年頃までは9月24日、平成12年まで10月24日となり今に至ります。
祭礼内容
担ぎ屋台8台、神輿1基が出祭。
全ての屋台が担ぎ屋台で、神輿や屋台とは違う迫力のある様子が見どころ。
夜になると、千葉県の無形民俗文化財に指定されている「平群の花火」を見ることが出来ます。
日中は各地区の曳き回しが行われ、夜になると平群小学校のグランドに全屋台が集合しお囃子の競演となり、これらは平群囃子の原点ともいえる本場の音です。
参加地区
荒川、井川(井野+川上)、犬掛、下、中、山田、吉沢、米沢の8地区。
有数の担ぎ屋台を曳き回す
荒川(山神社)
荒川は平群の天神社裏山側の地区で、同名ですが山田とは違いかなり山を登ったあたりに山神社を祀ります。
担ぎ屋台を所有。
平成20年に彫刻部材を除き屋台を一新しました。
それまでは、大正中期に製作された担ぎ屋台で、昭和42年に平群地区で一番早くタイヤを取り付けた区でもあります。
彫刻は、大正期に製作された屋台の部材をそのまま利用し、後藤門治郎義光・後藤喜三郎橘義信が手掛けたもので、後部の竜は門治郎が彫刻しました。
小祭屋台は平成元年に製作しましたが、平成6年頃から休止中です。
井川(井野+川上)(御嶽神社・鹿島神社)
井野は保田から入った最初の区で、そのすぐとなりが川上になります。
井野は区内に御嶽神社、川上は鹿島神社を祀ります。
担ぎ屋台両区で平群祭礼で出祭するための担ぎ屋台を1台所有しています。
後藤利三郎橘義久の彫刻が彫られています。
小祭屋台はそれぞれ1台ずつあり、昭和50年代頃から休止中で、部材のみだったものを昭和60年頃に改修しています。
犬掛(春日神社)

春日神社の様子
犬掛は平群の南で、南房総市旧三芳村との境にある区です。
南総里見八犬伝の犬掛古戦場跡や前期里見氏の墓などもあり、里見氏とのかかわりの深い所でもあります。
鎮守として春日神社を祀っています。
その入口には八房と狸の銅像があり、八房が狸に育てらたという伝説を(八犬伝自体もフィクションですが)再現しています。
後藤喜三郎橘義信の彫刻による担ぎ屋台を所有。
明治24年に製作されたもので、平群全地区がタイヤ付けを完了する昭和44年までにタイヤを付けたことがわかっています。
昭和24年に製作された小祭屋台は後藤滝治義光が彫刻がされていましたが、春日神社新築記念に建てられた観音堂に解体保存されています。
平成15年の神社の改修記念には小祭屋台が出祭。
 南総里見八犬伝ゆかりの地
南総里見八犬伝ゆかりの地
下(豊受神社)
平久里下ともいい、犬掛のすぐ上、中(平久里)のすぐ下に挟まれた区で、平群の中でも広い地区です。
平久里下はさらに大塚、中、原、長門、河前、長藤に分かれています。
犬掛の三叉路近くに豊受神社が鎮座します。
珍しい宮造り担ぎ屋台が出祭し、彫刻は後藤秀吉橘義雄によるものです。
小祭担ぎ屋台が5台(大塚、中、原、長門(長藤合同)、河前)あり11月23日に出祭しますが、全ての小祭屋台が出祭したのは平成21年8年ぶりのことです。
平久里下合同祭としては40年ぶりでした。
中(天神社)

天神社を正面から
平久里中とも書き平群のちょうど真ん中あたりになります。
平群の祭礼のメインとなる郷社天神社を祀ります。
出御する神輿の担ぎ手は各地区からの代表で担がれます。
祭礼の時に打ち上げられる花火は200年以上の歴史を持つとされ、千葉県の無形民俗文化財に指定されています。
かつては火薬から竹筒まで地元の人たちに伝えられた技術で行われていましたが、現在は花火師業者によって行われています。
以前使われていた竹筒は境内に展示されており、当時の面影を見ることが出来ます。
また、御祭神が菅原道真なので、受験シーズンになると合格祈願を願って多くの学生がやって来ます。
宮造りの担ぎ屋台が出祭。
昭和中期にもともとあった宮造り屋台と下区の屋台を交換し、平成元年頃に宮造り屋台へと大改修を行いました。
2代後藤義徳・稲垣祥三の部材はそのまま利用されました。
小祭用の曳き屋台は現在子供会が所有し、平成21年に17年ぶりに小祭を開催。
神輿も出祭し、祭りを盛り上げます。
台輪の幅は120センチですが、枠上の縁はそれをはみ出し114センチ。
このあたりでは重いことでも有名です。
江戸末から明治にかけての様式が見られます。
山田(山神社)
山田は平群の東側、鴨川市との境にあります。
山中、石川(石原+川辺)、東星田に分かれます。
中央を通る千葉県道89号線沿いに山神社を祀ります。
平成24年に新たに建てられた山神社は真新しいですが、その縁起は元禄年間に遡ることが出来ます。(創建年等は不明)
大正期に製作された担ぎ屋台には、後藤喜三郎橘義信による彫刻が彫られています。
昭和60年頃に大改修が行われてました。
小祭用の屋台は3台あり、1番新しいのは山中組ですが未整備で、石川(石原+川辺)と東星田は整備されてはいるものの、平成8年頃から小祭りは休止中とのこと。
吉沢(豊受神社)
保田から入った井野・川上との向かい下に吉沢はあります。
さらに吉井、西沢、沢又に分かれます。
豊受神社を祀り、担ぎ屋台が出祭します。
現在のものは昭和20年代に千倉で製作されたもので、後藤滝治義光による彫刻があります。
昭和50年頃に祭りを再開出祭。
小祭屋台は吉井、西沢、沢又の3台で所有していましたが、戦後から休止中で3台とも廃絶されてしまったようです。
 千倉ってどんなとこ?
千倉ってどんなとこ?
米沢(春日神社)
犬掛と同じ春日神社とを祀るようですが、区枠的にどのあたりになるのか勉強不足のためわかりません。
担ぎ屋台があり後藤系の彫刻が彫られているようで、現在のものは3台目と言われています。
明治期に製作され、平群地区で一番古い担ぎ屋台のようです。
小祭屋台は2台あるそうですが、部材のみで休止中です。
平群囃子発祥の地として南房総では有名です!
< 参考文献・サイト >
- 各地区の皆様!!!
- 房総の神輿―上総・下総・安房篇
平群は「平群囃子」発祥の地、だけじゃない?
平群の米沢からとされる平群囃子、実はここから始まったのはお囃子だけではありません。
米沢の人はもう一つ始めたことがあるそうです。
それは担ぎ屋台です。
神輿ではありません。
屋台です。
屋台って、いわゆる山車のことです。
南房総ではあえて、屋台と山車を区別していますが、曳き回すものという位置づけでいえば両者は同じもの。
山車や屋台などお祭りの余興物については、こちらの記事へ!
って、山車を担ぐの?
はい。
米沢の人は山車を担いでました。
ます?(現在進行形?)
とはいっても、初期のころのサイズはそれほど大型ではなく、どちらかというと神輿がちょっと大きくなったものだったそうです。
これが、時代を追うごとに大きく進化。
今でこそ屋台後部にタイヤをつけていますが、昔はなにもついてはいません。
でもちゃんと担いでいたそうです。
曳き屋台や山車、神輿を出祭させる人間から見ると、この担ぎ屋台はものすごく「すごい屋台」。
なんせ全部合体させたようなものなので、普通は曳き回すサイズのものを神輿みたいに担ぐんだから。
しかも、山間の地区なので上りあり下りありで曳き回すことですら大変なのに担ぐんです。
よほどの祭り愛がないと出来ません。
昔はそれだけ人も多かったし、みんな力持ちだったことが伺えます。
それを見越したとしても、すごい屋台です。
南房総では内陸に入るほど担ぎ屋台が多いのが特徴。
山間の悪路が多い所で曳き屋台を出祭させることは難しかったので、担いだ方が手っ取り早かったんだと想像が出来ます。
海側の地区でも担ぎ屋台がありますが、こちらは海町の住宅事情で狭い路地裏などを曳き回す事が出来なくて始まったもの。
ちなみに今でも鴨川の大浦の担ぎ屋台は担いでます。
 鴨川の担ぎ屋台
鴨川の担ぎ屋台
いずれにしても、この担ぎ屋台は南房総の立地に合わせて作られた独特の祭りの形。
そうしてまで祭りをやりたかった南房総の気質もわかるものです。
日本全国津々浦々の皆様、我が町も担ぎ屋台あるよ!という方、教えて頂けると嬉しいです。
もしかしたら凄くお祭り好きな地区だったりしませんか?
担ぎ屋台に平群囃子と、米沢の人はきっと好奇心旺盛で信仰心が篤く、お祭り大好きな人たちだったんですね。
また、平群では「平群囃子」の保存会や、休止していた小祭りを復活させ地域のつながりを深めようと努力している地区で、祭礼の維持や継承にとても関心の大きな地区。
そんなお祭りに熱い地区は、南房総の祭礼に貢献した地区でもあります。
本場の平群囃子を聞き、発祥の担ぎ屋台を見る、南房総のお祭りをはじまりを見るってきっと面白いです。
ちなみにここの天神社後ろの伊予ヶ岳(いよがたけ)は、千葉県で唯一「岳」とつくお山。
岩登りもできる登山家の中では知る人ぞ知る山。
山登りに来たら、南房総のお祭りもみていってくださいね~
平群の遊び情報はレジャー・体験・遊びの予約ならASOVIEW!や
じゃらん 遊び・体験予約などで色々紹介されています。
ちなみに地元人でも「え~そんなのあるんかい!」という内容も多々あり。
宿泊予約ならJTBホームページが大分細かく地域の宿泊情報を網羅しているのでおすすめ。
以上「おらがまち」まちこでした。
・ふるさと納税で文化財を守る。弱小文化財を守る一石三鳥の利用の仕方
・オリジナルのパワーストーンを作りたいなら「パスクル」 ![]() (広告)
(広告)
・南房総のお祭り一覧。全部見るには何年もかかるので、ご参観は計画的に!
・後藤義光の系譜を引く彫刻師・後藤流一門について。系図と人物概略
・金運アップ習慣【お財布専用ふとん】 ![]() (広告)
(広告)